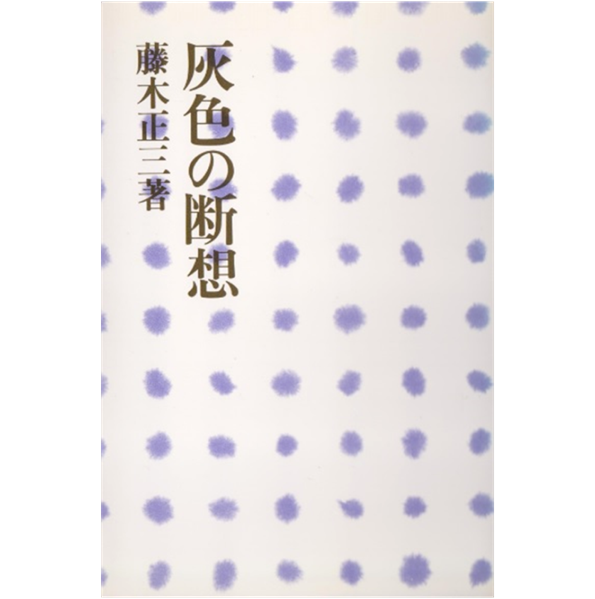|
熊谷哲夫氏に 目 次 灰色の断想 ひとり 土足 逃れ揚 自己評価 人間の構造 歪みの昇華 永遠 個人の歴史 個性 人間の尊厳 求道 時への抵抗 偶像崇拝 受身の深さ 連帯 個人として美しく 一人にして 生の単純 ゆっくり 生きる楽しさ 清い心 遍歴 前科者 公平 務め 無限の添削 不格好に生きる 見つめないで見る 正論と愛 うなずき合う 新しさ 悩みの時 人間の言葉 変わる 真理の圧力 面白く 志 徒労 本物 柔軟 宗教性 端的(一) 端的(二) 人生の幅 人間の幅 人間のセンス 自然に帰る 信と美 異なる期待 苦悩に助けられて 理想 社会 交わり 嫌なこと 端的に 単純 嫌気 人生の職人 堂々たる良心 自分を控える 襖悩直視 共に是れ凡夫 妬み もののはずみ 人生の実際 愛の退廃 自分を俎上に 偏向 醒めた人間 願い 高さの意識 徹底
置き去りにした問題 衰弱にあらず 人生の重厚 貴族 苦労 深刻と微笑 嫌みのない生活 美的に 残すまじ 跡 美しい幻想 信仰 心に労働を 測られる虚心 節度としての信仰 無力を選ぶ 美 礼 人生を祝福する 本来の重さ 信仰の受容 阿片に甘んじる 後退 祈り 神を語る 霊 相対性 一体感 具体的に生きる 複眼 格好がつく 恩寵 疑う 仕える ひ と り いろいろなことが入れかわり立ちかわり現われてきます。どれから手を着けるべきなのか、どれが一番大切な問題なのか、迷います。迷いながらも時にせかれ、決断させられて生きています。ですから生きるということは、そう厳密なことではありません。ただ、周囲の状況に押されたり、行きがかりに流されたり、自分への執着にまつわりつかれたりしていることを思えば、白紙の立場での決断は望むべくもないとしても、せめてそのような囚われた立場への点検を怠りなくすることによって、時への抵抗としたいものであります。 面 白 く 信仰を持たない人から受ける結婚式や葬式の依頼。なぜ、信仰なしに生きている平素の姿の中で、その人生の厳粛さを受けとめないのであろう。なぜ、平素の生き方とまったく関係のない、むしろ無視しているようなものに、人生の大事を装わせるのであろう。なぜ、そういう時に浮かぶ人間を超えたものへの思いを、平素の生き方の中に追究しないのであろう。不真面目というよりは、生きることへのその粗雑さが悲しい。ついでにもう一つ嫌なこと。結婚式の最中に、新郎に感激のあまり泣かれること。純情というよりは、男として未熟。 疑 う 神は唯一であるといわれます。しかし、神は一人一人の生活の支えとなり、道しるべとなってくださる方でしょうから、そのように一人一人の生活を形成しながら現われてくる方として、その人にとってはその人だけの神でもあるはずです。神が唯一であるとは、すべての人に神が同じように信じられるということではなくて、どんな人に対してもその人に添うように神が現われたまうということなのです。ですから、一人一人にとって神は異なると思います。人間にとって、信仰は所詮、神々の信仰に過ぎないのです。自惚れてはなりません。 人には何かそれぞれに負わされているようなものがあります。良いものを負わされている人、悪いものを負わされている人、さまざまですが、その負わされてどうにもならないものが、結局、その人の自分というものなのでしょう。お互い自惚れが強いので、いろいろと自分の姿を空想します。そして、それが思いと異なることになってしまうのを、運命とか宿命とかいって呟いていますが、その思い通りにゆかない姿こそ、実は本当の自分の姿なのです。運命などありません。あるのは自惚れだけです。運命は、自惚れの子供なのでしょう。 青春とは凝縮した人生なのです。だから、人生のすべてを見てしまったような経験を、若い日に誰しも持つはずなのです。以後の人生はそれに幅と深みを加えてゆくだけのものです。人生の不幸は短命ではありません。それは、以後の人生に幅と深みを期待するような経験を青年期に持たないこと、そして幅と深みを加えるだけの成年期を何かそれ以上の、新しい発見をする時期のように誤った期待をもって生きることです。人生は長命でないとわからないようなところもありますが、長く生きておればわかるというものではありません。 訴え求めて叫ぶ人の声が悲痛なものであれば、たとえその人の態度が独善的なものであっても、またその論旨が納得できないものであっても、理解するよう努めましょう。しかし、もし自分の訴えがそのようなものであったら、黙りましょう。なぜなら、肺腑をえぐるような悲痛な声も、決してそれが偽りだというのではありませんが、未整理であり、それは誇大化して偽りになるからです。訴えに際して、念々思いをいたすべきは、心の整理であります。整理された心から出る訴えは、柔かく、さらっとした表現を必ずとります。 顧みてくれる人がいないような時にも、見回せば、共にいてくれる人は一人ぐらいは必ずいます。批判する人がいないような時にも、よく見れば、反対している人がかなりいます。それが世間というものです。世間のそういう一面的でない性格のおかげで、私どもは、時に失望しても思いつめないですむのであり、時に傲慢になっても反省へと導かれるのであります。世間は、たしかに雑然かつ茫洋としていますが、それは世間の叡智ともいうべきものであるのです。世間は決して、私どもを追いつめはしません。しかし、甘やかしもしません。 礼拝は神を拝むことといわれます。しかし、私どもは限りあるものなのですから、永遠なる神を云々したり、拝んだりということは簡単なことではないのです。それは、神の前でおののく、つまり自分の悲惨を認めしめられることを抜きにしては、ゆるされないことなのです。悲惨を内に見出すことなしに礼拝するなど、あり得ないことなのです。礼拝とは、上を仰いで神を拝むというよりは、内を見つめて自分の悲惨から目をそらさないことなのです。その意味で、良心の苦悩はそのまま礼拝であり、死は最も厳粛な礼拝の時にもなるのです。り、死は最も厳粛な礼拝の時にもなるのです。 気まぐれな心もあります。打算と感情に流されている心もあります。心はいつもそのように何かにとらわれているものです。ですから、そのとらわれから自らを解き放つことが、心に常に負わされている課題なのです。そして、この課題を果たしている限り、人は自ら心で決めたとおり何をしようと自由なのです。人はよく何をするかに重きを置きがちですが、そういうことはどうでもよいのです。大切なことは、心がこの心の課題を厳密に担っているかどうかということなのです。心ほど巧妙に自分を欺く曲者はいないからです。 良いことがあれば感謝をする、当然のことですが、良いことがなければ、不平に変わるかもしれません。何でもかんでも感謝する、その素朴な善良さには打たれますが、安易な繰言という感じもしないではありません。それよりも、どんな時にも黙々と生きている人を見ると、深く人生に感謝している人という感じがするではありませんか。感謝というのは、あれこれの人や事柄に対する反応ではなくて、他人と比べずにただ自分を大切に生かしてゆくことに日々つとめる、そういう人生全体に対する肯定のことでありましょう。 本当にあったことを言い、本当に思っていることを語り、自分の真相を隠さず述べても、まさにそのように本当を語ることにおいても、立派に嘘をつくということがあるものです。というのは、本当というものは、単に真実とか正直とかいうことではなくて、恥をかいたり苦しんだり傷ついたり、とにかく自分と闘う痛苦を、本当であるために身に負うことにあるからなのです。外的な挙動からうかがい知ることのできない内面の世界のそのような痛苦に、本当というものが属することを知ったなら。人は寡黙にならざるを得ません。 どれだけ多くの人が高い評価を与えてくれても、そして、それはたしかに嬉しいことであり自信をつけてくれることではありますが、かといってそれで満足するのは、いかにも人生に対して張りを欠いたことであります。人間はあまりに甘いので、そういう評価より自分を強いてでも引き離してゆく、つまり人間からの別離を生きるということなしに、人生に対する真面目をあかしするすべはないでしょう。好評を博することを願うよりは、この別離の姿勢をもって心に張りを持たせて生きることを、願いとしたいものであります。 人にされることは小さいことでも大きく、人にすることは大きいことでも小さく見なしがちですから、加害者ではないかと常に自問自答しましょう。そうすれば、人のすることも自分のすることも正しく見るのに、いささかは役立ちましょう。また、わずかな優位でも誇り、人を見下げがちですから、差別者ではないかと常に自問自答しましょう。そうすれば、特権的高慢や差別される人の悲しみに気づくのに、いささかは役立ちましょう。そういう自問自答を常に課すのを自虐に過ぎるという人は、まだ自分の虚無を見ておりません。 人生の意味を問い目的を問うて、多くの答えが出されてきました。しかし、人はそのいずれにも満足しませんでした。そして、答えのないままに生きてきました。これからも同じことです。これを不真面目と思ってはなりません。答えがないということは、答えはなくとも、とにかく生きるのが人生だということを示しているからです。それは、人生は答えで生きるものでなく、問いで生きるものであることを教えているからです。人生にとって大切なことは、答えを得ることではありません。不可解に耐えて問い続ける忍耐であります。 深刻な表現でひねったことを語る人がいます。深い人かというと、必ずしもそうではないので、深さを装うポーズの場合だってあるのです。私どもの心には、たとえば光よりも闇を愛すといったような、「逆らう構え」のようなものが常にあるわけで、ごま化しの擬態が何事につけても巧妙に入り込んでくるのです。あまりにそれが巧妙なので、自分の擬態に気づかない位です。ですから、何に対するよりも先ず、逆らうように構えている自分の心に対して警戒を怠ってはなりません。この警戒から解放される時は片時もないのです。 悲しいこと、淋しいこと、たくさんあります。もちろん人生には、愉快なことも少なくありません。しかしどちらかといえば、つらいことの方が多いと思います。第一、最後には死なねばならないのですから、明るい面ばかりを見て喜んでいるわけにはゆきません。それでも、生きる知恵の最も深い姿は、人生を喜ぶことの中に隠されているのです。なぜなら、悲しみには主観に流される弱さがありますが、喜びには主観に流されないで事実に即し得る強さがあるからです。人生は、悲しみでは見通せません。喜びでこそ見通せるものです。 形式、無内容の代名詞のようにいわれます。事実そのような場合も多いのですが、形式よりも内容だ、と自分の実感を盛ろうとした結果が、独善的満足に終わることも少なくありません。形式は一つの客観性です。無内容になる危険性をはらんではいますが、実感に頼って主観に流される誤りから守ってくれるものでもあるのです。実感は大切にせねばなりませんが、所詮私の実感なのです。それのみに依拠するのは危険を冒すことです。なぜなら、形式を無視して、しかも主観に流されずに自らを持し得るほど、人は冷静ではないからです。 親子というものは夫婦と違って、放っておいてもその関係は切れません。ですから、精神的存在になるために人は、切れない親子の関係からは離れ、切れる夫婦の関係においては結びついてゆく努力をせねばなりません。およそ精神というものは、放っておいても成り立つ甘えた関係の中では成長するはずはないのです。子は離れねばなりません。親は離さねばなりません。これは冷淡ではなく、冷静なのです。冷静に親の限度に留まり、子が精神的存在になってゆくように自ら離れてゆく時、親もまたはじめて精神的存在になるのです。 信仰は喜びをたしかに与えてくれはしますが、しかし、それは喜びのためのものではないのです。何のためかと言えば、人生の根底にある問題を明らかにするためと言えましょうか。信仰は人の醜さを明らかにし、それから目をそらさせないように拘束することをもって第一義とするものなのです。そういう意味で信仰は、喜びよりは苦しさを与えるものであり、そしてまさにその苦しさにおいて、人生の根底に触れている故の安定感を与えるものであるのです。信仰の与える喜びというものは、結局この安定感の別名にほかなりません。 なべて筋が通らぬことを拒否するのは大切であり、そのような拒否によって問題が明らかになり誤りも正されてゆくことは事実ですが、それにもかかわらず拒否の姿勢には人生への誤解があるように思います。拒否不可能な死によって決定的に人生は限られているからです。拒否とは人生に明解を求めることでしょうが、ついに明解を与えず、ただ受容を求めるのが人生なのです。拒否の姿勢が真摯であるのに平板浅薄の感がつきまとい、受容の姿勢は退嬰無気力にみえて人生の底を見通しているような感を抱かせるのは、その故なのです。 よいことがあれば喜び、いやなことがあれば嘆き、状況次第でふらふらしながら人生に注文や苦情をつぶやいているのが、私たちです。しかし人生は、どんな文句も受けつけてくれないような厳としたところがあって、その事実に納得させられて黙ってしまうよりはかないものであるのです。そのように納得させられた時、人は寛容になります。寛容とは、人を責めず、差別せず、受け入れる広さですが、それは、人生に納得させられた知恵に伴う品性なのです。この知恵のない寛容は、自分の無内容を隠すごまかしに過ぎません。 自分の立っているところがくつがえされるような出会いがあります。法にふれず世間も問題にせず良心にとがめるところもないのに、それだけでは善いとは言わせないような出会いであります。そういう出会いを知らない人なら問題にしないようなことが、そこでは問題になります。そして、そのような問題を見つめているのでなければ、人間が人間にならないような、そういう出会いがあるのです。自分を豊かにしてゆく出会いはもちろん大切ですが、人間それだけでは迷子になります。人間はどこかでくつがえされねばなりません。 矛盾とたたかいながら自分の納得するものを掴もうとし、いろいろの可能性を試みながら自分の充実を計ろうとする。いずれにしても人生は、自分を託し切れる真理を求めての模索です。模索されている真理の方からいえばそれは、その真理が現われてくるのを妨げているものを取り除いてゆくことなのです。ですから人生は、なにかを創造することではなくて現われてくる真理を正確に写すこと、無私に極まる厳密さで写すことでなくてはなりません。生きる姿勢の基本は、創造ではなくて模写であります。創造はすでに終わっております。 個人の人権と自由を守るために、そして社会の正義と平和と向上のために働きをする、それが宗教本来の仕事のように思われがちですが、そしてそういう面もたしかにあるのですが、それらの働きのすべてがたとえ実を結んだとしても、その一切を空しくするような無意味さが人生にはあるわけで、宗教の関わるべき固有の領域はそこなのです。無意味さに意味を見出したり、あるいはそれに耐えたり、いずれにしても無意味さに魂の凍るような虚無感を味わいながらも、それから目をそらさずに立ち向ってゆく、宗教の仕事はそれです。 不動の信仰とは、信じることにおいて迷いのないことなのでしょうか。そうではありません。私たちの生活は常に不条理に揺れていますし、私たち自身も常に愚かな迷いを続けているわけで、信仰もその点例外であるはずはないのです。人生の営みはすべて迷いの中にあります。ですから、迷いからの脱出を願うのではなく、迷いこそ正常な生の姿と受けとめることこそ大切であり、そう受けとらしめるのが信仰というものでしょう。そして、迷いの中で不動を求めずひたすら虚心を求める、それが信仰の不動というものであります。 信仰の陥りやすい、そして致命的な誤りは、一定の神学なり教派なり政治的態度なりに固定した確信に、それがなってしまうことです。つまり、一つの私事に信仰をしてしまうことです。信仰の本来は、自己執着に基づくはからいを脱却することですから、たしかにそれは、一面私事でよいのですが、しかし他面、私事になってはまったく意味を失うものでもあるのです。この矛盾した性格にふさわしい信仰の姿、それは迷うということです。信仰は迷いを解くことのように誤解されていますが、実は、誠実に迷いに常住することなのです。 利己的という意味ではなく、人の意見に耳を傾けないという意味でもなく、客観性を無視するという意味でもなく、ただ自分の生き方と語ることとの間に隙間がないようにという配慮から、自分のことしか語れない無器用に純粋な人がいます。もちろん世の中には、自分の生き方にまったく関係のない一般論を立派に論じられる器用な人もいます。どちらがどうとも言えませんが、信仰というものが無器用な人のものであることだけはたしかです。信仰の世界は万人に開かれているようにいわれますが、実際は決してそうではありません。 世の中には醜いこと、不正なことがたくさんあります。ですから、そういう世の流れを批判するのは当然であり、またせねばなりませんが、しかし、どんなに超然と批判的に生きても、所詮はその流れの中の一人であるわけで、従って批判をするということは、する資格のないものがしているような後ろめたさを常に伴うものであるはずです。もし、自分だけは超然としていると思っているのなら、それは人生を怖れて生きることに疲れた者の傲慢であります。後ろめたさのない批判、これほど人格の疲れを示すものはありません。 時の経過というものは、私が今日、明日、そして次の日と前進してゆくことの中にあると考えることもできますが、逆に、私はじっとしているのに時の方が向うから動いてきて、そのために昨日、今日、明日を経験させられると考えることもできます。私が動くのか時が動くのかなんとも言えませんが、動けないほどに卑小な自分を思えばやはり時が動いているように思います。生きるということは、未来を目指して動くことではなくて、この卑小の一点に突っ立って流れくる時の中で動かないこと、まさに動かないことなのでありましょう。 仕 え る 自ら心に問うて恥じるところがなければなにをしようと自由ですが、それはもちろん気位ということではなくて、人生には必ず選ばねばならないような絶対的に正しい道はないということなのです。ですから、この自由は逆に、求められれば自分の心にそわないことでも敢えて選びとらせる根拠ともなりましょう。つまり、自分を軽くみなしてとらわれず、人に仕えるように支えてくれるものともなりましょう。仕えるというと、謙遜とか奉仕とかを考えがちですが、そうではなくて、それは自分にこだわらない自由な人の姿なのです。 仕えられたいと思うのは当然ですが、仕えることのほうが大切であることは、お互いよく承知しているところです。とは言っても、それは分の悪い辛抱の大変いることですから、どこか世離れしていなくてはできません。世離れといえば時流に抗して生きることなどと考えられますが、とても仕えることにはそれは及びません。なぜなら仕えるというのは、単純に世を離れることではなくて、世の中に深くいながら世を離れることだからです。世に流されない自由な生き方を守ってくれるのは、抗する姿勢ではなく、仕える姿勢なのです。 恥をかいても何とも感じないというようになれば、人間はたしかにおしまいです。恥を知らねばなりません。しかし、恥をかかずに生きておればそれでよいのかといえば、そうでもありません。真理というものは、それに従って生きてゆこうとするものに、卑しめられるままに屈従に甘んじることを要求するものなのです。ですから、恥をかかずに生きようとする人は、真理を志向するとか使命に生きるとかいうこととは本質的に無縁に、自分に流されているのです。流されずに生きようとする人は、恥の持つ高貴さをわきまえねばなりません。 人と広く交際するのはよいことですが、それが苦手という人もいるわけで、それはまたそれでよいのです。人の世話をするのも結構なことですが、迷惑にならぬように自分の生活だけを守っているのも悪いことではないでしょう。人に頼まれると気軽に引き受けるのと、あまり関係のないことには一切手を出さないのと、どちらとも言えません。総じて人間の交わりにおいて大切なことは、眼の前の人が助けを求めて伸ばす手を振り払わないこと、それだけです。それさえあれば、人間の交わりなど好きなようにやればよいのです。 当り前の話ですが、人生には終わりがあります。栄光も幸福も一切が無に帰する時がくるのです。愛もこの到来を止めることはできません。ですから真面目に生きようと投げやりに生きようと、あまり相違はないのですが、それでも無に終わるものとして人生を見れば、自分に執着して生きるのは愚かなことであり、執着しないで愛と善行に生きる方がまともだと思います。愛と善行は別に称揚されるようなものではありません。それは、人生の終わりを透徹した目で見ている人の、それよりほかに生きようのない姿なのであります。 何かを手にいれる、何かをする、何かになる、とにかく何かを目指して私たちは生きがちです。しかし、精一杯生きて志半ばに倒れ、何をも得ない人は、果たして人生の失敗者なのでしょうか。泉のようなものが、人生にはより添うてあるものです。ひたすら自分に厳しく人に優しく生きる人には、いつでもどこでも誰にでも湧いてくれる、そんな優しい泉があるのです。この泉に気づくこと、そして飲むこと、何を得ずとも人生はそれで決まります。人生の目的は、向うの方にはありません。寄り添うて横に、いや足もとにあります。 共に苦しみ共に喜ぼうとしても、こちらの気持が相手に通じるとは限らないわけで、人に関わるということは、相手の対応を度外視して一方的に関わり続けるという徒労を、究極において要求するもののようです。徒労の継続こそ関わりの真骨頂とも言えましょう。一見無関係に思える両者の間にも、徒労による関わりが深く秘められている場合もあるのです。この世に神があるとも思えませんが、それも果たして神の存在しないことを示すのか、それとも深く関わりたもう神の惨憺たるたる徒労を示すのか。自分の惨恢を思うて、私は後者にかけます。 「何回人をゆるしたらよいのか」。こんな疑問が心に浮かんだら、もうゆるしを語る資格はないと知るべきであります。ゆるしというのは、相手に寄り添おうとすることにおいて、その人がどれほど裏切ろうと、迷惑をかけようと、不変であるということなのであり、またその人の過去からも、世間のうわさからも、性格や教養からも、その他一切から超然たりうるということなのです。この不変と超然、つまり自由こそゆるしのいのちなのです。「何回まで」などという所には、不自由な人間の賢さはあっても、ゆるしはありません。 率直に言ってくださいと頼んでおきながら、率直にいわれると途端に不機嫌になるような勝手さがあるのですから、私たちは率直さを押えたやさしい言葉を、一概に朧だと言い切る資格はありません。そういう言葉でどれだけ、自分を取り戻させてもらっていることでしょう。その言葉の意外なやさしさで、私たちの心はいつも復活しているのではないでしょうか。真実が、復活の力を持つ時は、それが生まで語られる時ではなく、意外なやさしさという嘘をまとうた時なのです。裸の真実は、必ずしも人を生かしません。殺しもします。 愚かな浅ましい生き方を認めるわけではありませんが、頭からそれを否定するのは人間の現実に対して誠実を欠くように思われます。お互い支離滅裂な心を生きているわけで、その裂けた心のひだの深さを見れば、浅ましさを簡単に否定するのは、表面的な整合にもかかわらず、人間の生まの現実に対しては不誠実に思われてなりません。心のひだに触れてゆくしなやかさが求められます。そして、このしなやかさこそ、人間の現実に対する誠実なのです。人に対する温かさは、この誠実から湧いてきます。妥協からは湧いてはきません。 神を信じるということは、普通の知識からみると疑わしいことであり、世間の常識からみると愚かなことであり、円満な教養からみると偏ったことであり、富と力で動く社会からみるとお人好しなことであり、いずれにしてもちょっと恥ずかしいことであるのです。もし恥ずかしさを感じないのなら、その信仰は自己流の信念に過ぎないか、世間が信仰をどのように評価しているかに気づかないほど鈍感であるかでありましょう。信仰を恥じるということは決して悪いことではありません。それは、信仰の弱さではなく、健全さなのです。 愛することは与えることだといわれますが、そしてそれはその通りなのですが、もう少し丁寧にいえば、それは与えることによってはじめていやされるような渇きを心に抱くことなのです。与えて心の渇きをいやす、それを愛というのです。愛の問題は、愛する対象の問題でも、愛の結果の問題でもなく、何に心は渇いているかの問題なのです。与えることによってのみいやされるような渇きを心に抱いているか否かの問題なのです。そういう渇きなしに与えるのは愛ではありません。愛の純度は、渇きを深める努力にかかっています。 使命とは何かという問いは、使命の本質からいって問いとして間違っています。使命は生の転換を機に、自分の存在の底から突き上げてくる拘束のようなものですから、この転換なしに理解しようとしても無理ですし、転換を味わったものは、使命を自明のこととしてもはやそれについて問わないからです。ですから、日常において当然としていることを、根本的に疑う問いか、使命とは何かという問いに先行せねばなりません。この問いによって日常性からの転換を味わわしめられているものの悠悠、それが使命の本質なのです。 どの程度の力を持っているのか、どのような生き方がむいているのか。自分のことは自分が一番よく知っているようで、なかなかわかりません。どうしてこうも自分を的確に見る目がないのか。おそらく自惚れや野心や見栄などが目を曇らせるのでしょう。ですから自分で選ぶよりは、人から求められたところに生きる道を選び定めてゆく方がよいのです。消極的かもしれませんがそうすれば、比較的正確に自分を見ることができましょう。なぜならそれが使命に生きるということであり、目から曇りを取り除くのは使命感だからです。 真理を発見しうるほどに私たちは偉大ではなく、また発見しうるほどに真理は小さくもありませんから、およそ正しいと思われることには何にでも思いをいたしてゆくよりほかありません。たとえ主張を異にする人が言ったとしても正しいことは正しいのですし、その正しさを認めることが不利を招くような場合でも、やはりそうなのですから、およそ正しいと思われることには、変節と思われるほど自由に心を開いてゆきましょう。それは変節ではなく、ついに発見することのできない真理が、隠れたままに与えてくれる自由なのです。 楽に安全に早く、要するにできるだけ近道をして目的に達したいと誰しも思います。しかし、目的に達することだけに意味があるのではなく、途中の景色を眺めたり、道に迷うて苦労をしたり、思いがけない人に会ったり、ということも大変意味のあることなのです。そして、近道を選んで事足る場合ももちろんありますが、回り道をする面倒さを避けてはその意味のよくわからない場合もあるのです。人生はあとの方です。無理に回り道をする必要はありませんが、少なくとも近道だけはするまいと覚悟して生きたいものであります。 人間は助け合って生きてゆくものですから、社会的責任を果たすことの大切さはいうまでもありませんが、さらに大切なことがあります。それはひとりを自覚することです。ひとりの自覚とは、無限の時の流れの中で味わう無常感、我意から自由になれない罪悪感のことです。それは決して社会に対する無関心、無責任のことではなくて、そのような卑小なものと自覚して、同病相憐れむ思いで同一水平線上にお互い立つ、平等の自覚なのです。その意味でひとりの自覚こそ、社会的責任を果たすための前提といわなければなりません。 無心というのは、考えるのを止めることでも、自分を忘れるほどに夢中になることでも、無意識になることでもありません。それは、澄んだ心であります。さまざまな欲望で必ず濁っているのが心ですから、それらを鎮めた心です。もちろん欲望は、じっとしていると自然に澄んでゆくものではありませんから、鎮めるには工夫が必要です。苦しみを選びましょう。欲望は結局、楽な、やりたいことを選びとらせようとしているからです。無心とは、自分の負うべき苦しみが見え、そして、それを自らに課してひるまない心です。 伝道というのは、道を伝えて信仰に導くことではありません。道は、伝えるものではなくて生きるものだからです。煩悩にあえぐ私たちがそのままに受け入れられて生かされる、これしか生きる道はないとするのが信仰というものでしょうが、幸福を求めて生きたり、豊かさを求めて生きたり、楽しさを求めて生きたり、人生を生きる道は数多くあるわけで、その中でこの生かされて生きる道以外は選ばない、断固としてそれ以外に生きる道を選ばない、それが伝道ということなのです。伝道の生命は、この断固さにかかっています。 人はそれぞれ重荷を負って生きています。そして重荷は自分で負うよりほかありません。いささかの助けを他に期待し得るとしても、代わってもらうわけにはゆきません。それが人間の事実です。ですから、重荷を取り除いてあげるよりは、その人がしっかり重荷を負い切るよう助けてあげましょう。その意味で、その人をその人としてつき放すのが、人間の事実に適った親切というものです。人間の交わりは、そういうつき放しを、お互いかわしながら、それぞれに重荷を負うてゆく、いわば戦友同志の交わり以上であるべきではありません。 日々のつとめを精一杯果たし、家族団欒を楽しむ、この日常性を軽蔑してはなりません。人生は鋭い問題意識を持った人だけが深く生きうるような、そんな特別なものではない筈です。平和に楽しく平凡に生きるのも、言われるほどに不真面目な浅いことではないのです。それは側から見るほど安易な生き方では決してありません。耐えずして、戦わずして、迷わずして、どうしてそのような平凡が生まれましょう。人生の深さは、意識の鋭さで測るものではないのです。たとえ平凡であっても、経験の厚さで測るものであります。 人数より数の少ない椅子の周りを回りながら、椅子の取り合いをするあのゲームのようなところが、人生にはあります。必ずはみ出す人がいるのです。人生がそういうものだとわかると、そうなるまいと貪欲になるのは人情ですが、逆に誰かがはみ出すのなら進んでそうなろうとする生き方もあるわけです。しかも、それを人を愛するためにといった立派なこととしてではなく、むしろ極く自然に美しい満足のようなものをそこに感じて、そうする人がいます。粋な生き方であります。信仰生活には、この粋がなくてはなりますまい。 すべては、はかなく頼りなく過ぎてゆきます。どこを見ても、何を見ても永遠に続くような絶対的なものに出会えません。一体、それはどこにあるのでしょう。死後の世界に求めるべきなのでしょうか。現実の生活に全く無縁なところにあるのでしょうか。そもそもそのようなものは無いのでしょうか。そうではありません。現実の生活の裏側に、それはぴったりくっついているのです。現実に執する目には見えないだけのことです。ですから、日々を無きが如く執せずに生きるなら、人はどこにおいても永遠を味わうでありましょう。 敵を愛することは最高の美徳のようにいわれますが、よく考えてみると、敵など現実の生活の中にはいないのではないでしょうか。誰が敵か、具体的に考えてみましょう。嫌いな人はいます。腹の立つ人、不愉快な人もいます。しかし、敵というおそろしい言葉で呼ぶべき人は、そうやたらといるものではありません。敵を愛するという美徳を、滑稽な気負いにしてしまう位に、現実というものはお互いさまなものです。仮想の敵に備えるよりは、お互いあまり変わりはないのですから、ゆるしゆるされて生きてゆく方が、足が地についています。 一 相対化の視点の根拠 デンマークの評論家V・セーレンセンはその著『あれでもない―これでもない』(Villy Sorensen:Hverken‐Eller, Gyldendal,1962)で、根源的・批判的に物事を問うということは、社会的領域においても、科学的領域においても、宗教的領域においても、以前は一面的な戦いでよかったが、今日のように価値が多様化している時代においては、それでは抽象的であって、二面的な戦いにならねばならぬ、といっている。つまり、さまざまな価値の中から一つを排他的に選択するのではなくて、共存する諸価値との対決を持続することが根源的批判になる、という意味であろう。今日は、価値の単一化が対決の持続に耐え得ない精神の弱さを意味し、また事態から目をそらすことを意味する時代である。だから、一つの価値を絶対化し有とする精神の弱さに抗して、無を建てて一切を相対化してゆく視点の根拠が求められる。ところで、相対化か他との比較における相対化、つまり密閉された状態から解放された状態に出て自分を見直すという程度での相対化であるならば、きわめて不徹底であり、それは絶対的なものとの出会いにその根拠を求めなければならない。 今日における愛の問題の一つは、この相対化の視点の徹底した根拠をめぐってのことであろう。というのは、キェルケゴールが『キリスト教の修練』の中で「キリスト教は、牧師が涙っぽく、また不真実に人に教えるように、さまざまな温和な慰めの原理の一特製品として、この世に来たのではない。そうではなくて、それは、絶対的なるものとして、来たのである。このことを神は愛からして欲し給う。しかし、そのように欲し給うのは、やはり神であり、神はその欲することを欲し給うのである。神は、人間によって、人好きのする人間的な神に作り変えられることを欲し給わない。むしろ神は、己れが人間を作り変えることを欲し給う。しかも神は、愛からして、そのことを欲し給うのである」(井上良雄訳、角川文庫、傍点訳者、九〇頁)といっているからである。神の愛とは、神の側からいえば。その意志に従って人間を作り変えることにおいていささかもたじろぎたまわない、ということである。そして、人間の側からいえば、最大の呻吟と苦痛の中で直接性が否定されることである。神の愛こそ、安住、固定をゆるさず反省を無限に迫るものとして、相対化の視点の徹底した根拠であろう。「あれか―これか」と決断された神の愛こそ、「あれでもない―これでもない」という果てしない相対化の視点の根拠となる。 「あれでもない―これでもない」は、(一)単なる懐疑ではない。独断的主張に対する批判ないしは反論としての懐疑ではない。(二)また単なる複合でもない。複数の諸価値の矛盾する面を退けず重なり合わせ、それを二つながらに生かして一つの価値とするような複合でもない。川村二郎氏がその著『幻視と変奏』(新潮社、一九七一年)の中で、ドイツの作家ノサックの『未知の勝利者』を評して、この作品の中で注目すべき点として歴史に対する視点の定め方の問題をあげている(二三頁以下)。視点の一つは歴史を厳密な科学的方法によってのみ接近し得る客観的総体と見て、そこに個人の力が作用するとしても、その個人は総体の複合した力関係の一環をなすものに過ぎず、この総体に寄与することにおいてしか存在の理由をもたないと考える、いわば外側からの巨視的な鳥瞰の視点である。視点のその二は、そういう史実に対する科学的方法のみでは埋めることのできない、私的な、もののはずみが演じる重大な役割に注目する、いわば内側からの微視的な私的経験の視点である。そしてノサックは、そのいずれかを排他的に採るのでなく、二つの視点にそれぞれの意味を認め、一見相矛盾するこれら二つの視点から事態を観察しながら、ついには一つにからみ合わせてしまう複合的視点を目ざしているとされる。しかし、「あれでもない―これでもない」は、そういう複合ではない。複数の価値がそれぞれ単独では不十分であるから、相互に補足させたりあるいは相互に衝撃し合う関係に据えて、そこにもう一つ別の価値を見出そうとするような複合ではない。(三)「あれでもない―これでもない」はまた、いわゆる不可知論でもない。人間の認識はすべて感覚器官に生じる印象及びそれに基づく観念であって、それ以上に出ることはできないから世界の認識は不可能である、とするような不可知論でもない。(四)「あれでもない―これでもない」は、絶対性の内在に基づく価値の相対化なのである。絶対性は啓示されて内在するやいなや、直ちに絶対的なものではなくなる。内在性が絶対性の領域を侵すからである。絶対性は内在的には存在し得ないものとしてあるより他はない。それは有として自己を啓示し得ない。それはしたがって「あれでもない―これでもない」という形においてしかあり得ない。「あれでもない―これでもない」は、認識の不可能性のことではなくこの絶対性の内在のことなのである。神の愛が「あれでもない―これでもない」という相対化の視点の根拠となるのは、この絶対性の内在としての意味においてである。 そのようなものとして神の愛は、何らかの意味において「ある」ことを志向するものを一切拒否し、それゆえ神の愛に従って反省してゆく誠実(キェルケゴール)を問題にし、客体としての価値の選択を問題にしない。なぜなら、あれこれの価値は、「あれでもない―これでもない」ものとして、所詮は絶対性の痕跡ないしは影であって、絶対性そのものではあり得ない反面、「あれでもない―これでもない」と否定されながら、「あれも―これも」絶対性に接しているからである。それらの価値は、思考的整合性、歴史的客観性、科学的普遍性などに関係なしに、また部分的・断片的であっても、逆に全体的・総合的であっても、絶対性の開示を担うという意味においては等しいのである。かくて、神の愛は絶対性の内在として、一つの価値に安定しようとすることに対しては、反省の誠実の要求であり、価値の選択においては、「あれでもよい―これでもよい」という相対性への解放である。だからそこでは、(一)いかに正しい価値を選択しようとも、誠実の要求から解放されることは決してあってはならないのである。誠実とは、人間を作り変えることにおいていささかもたじろぎたまわない神の爰に従うことであり、それは外面的なもので測り得ない内面性のこととして、いかなる価値を選ぼうとも、厳密に要求され続ける。この内面的反省の無限を誠実というのである。そして、(二)そこでは、一つの価値を、たとえそれが正しいものであっても必ず選択せねばならないという窮屈さがなくなる。その価値に反対、否定するからではなく、むしろそれに賛成、肯定しながら、しかもそれに身を任せ切れないようなはみ出しが、そこでは認容されるからである。はみ出していることが、わがままでも臆病でも逃避でも、そして誤りでもなく、正当な権利としてそこでは認容されるのである。正しいものは必ず選択するべきであるという考えは、そこでは、このはみ出す権利を奪う、正しさの窮屈、となるであろう。要するに、相対化とは、その根拠を神の愛に置く時、内膠的には無限の反省としての誠実の要求であり、外面的には、正しさの窮屈からの解放、のことであろう。 今日における愛の問題の一つとして、相対化の視点の根拠をめぐって考えたわけであるが、われわれを窮屈にしている多くのものの中から二つを例にあげて以上のことを少し具体的に述べてみよう。その(一)日は性格をめぐる窮屈さの問題である。血の繋がり、育った環境、出会った人々、経験した出来事、そのようなものが、意識の奥底に潜在する深い心理性に刻みつけられるものがある。刻みつけられたものが、一般的、普遍的なものである場合はよい。しかし、それが特異な、時には一般的なものへ回復不能ですらある病的な場合がある。個人の歴史が刻んだ性格のその歪みは、必ずしもその人の責任ではないけれども、現実的にはその人が全面的に負わねばならない。そしてそこに、その歪みが一般的なものに対して感じる窮屈さの問題が出てくる。その(二)は、政治、社会をめぐる窮屈さの問題である。たとえば日本基督教団第一五回総会期の歩みにっいての議長の総括報告の中に次のような一節がある。「今次の万博問題は全教団に深刻な影響を与えた。われわれはこのことをただ対立、混乱として見るのではなく、そこで問われ求められたことがらをしっかりと受け止めたいと思う。日本の教会の過去への反省から、教団は政治・社会の問題を自己の責任として負い、正しい発言と行動とを通して『見張り』の使命を果たさねばならない」。まったくこの通りである。これに反対するのではない。しかし、窮屈さを感じる。それは、族的・政治的なものとキリスト教的なものとを内面的に融合して社会的主体性をうちたてた、グルントヴィヒに対するキェルケゴールの嫌悪に似ている。客体主義に対する主体主義の反発というのか。とにかく個人が政治・社会の問題において感じる窮屈さの問題である。 二 性格の歪み 「神の認識によって、その文体と力とには、時代の痕跡をとどめぬもの」。エドマンドーブランデンは、エミリーブロンテの次の詩をこのように評している。 わが魂は怯儒ではない。 嵐に傷む世界に在って戦慄するものではない。 私は見る、上天の栄光のかがやきを、 われを恐怖から守る信仰のかがやきを おお、わが胸のうちなる神. 全能にして遍在なる神よ、 不滅の生なる私が、御身にありて力を得る時、 わが内に安ろう生命よ 人心を揺り動かす百千の信条の空しさ 言葉にも尽しがたい空しさ。 ・・・・・・・・・・・・・ (阿部知二訳 The Bronte Sisters 研究社、一三八頁以下) 時代の痕跡をとどめず、とブランデンはいったが、もちろん時代を超え社会を超えて、幽鬼のごとく彼女が生きたわけではない。一八一八年から一八四八年まで、イギリスのヨークシヤに彼女は生きた。時は産業革命の時代であり、その地方には織物工場も多く、当然、革命の進行に伴う失業者の増大やさまざまな社会不安を彼女は見聞したにちがいない。いわゆるラッダイト(Luddite)蜂起も知っている。しかし、彼女はそのような社会的問題には関心を示さなかった。彼女の関心は、その著『嵐ヶ丘』に象徴的に示されているように、霊肉の葛藤する魂の問題にあった。一切の精神的なものを破壊して止まない条理を絶した人間の肉的な本能、しかもなお消し難く交錯する天上的なものへの凝視が、そこに描かれている。貧富の問題や財産所有の問題、要するに時代の問題は、結局彼女の魂の問題にはなり得なかったようである。なぜ産業革命という激励の時代に生きたにもかかわらず。その目はただ心内にのみひたすら注がれるに終わったのであろうか。 ほとんど家に閉じこもって社会生活の経験を味わわなかった彼女にとって、一八四二年のブラッセルズ遊学は、時代に開眼する大きな機会であったと思われる。しかし、事実はそうではなかった。彼女は開眼するどころか一層、時代に背を向けるようになったらしい。伝えられるところによると、「……寄宿舎の大きな室の一番隅のところをカーテンで仕切・て、そのかげに夜は眠り、昼には教室の一番うしろにすわり、休の時間などには校庭の並木のかげを歩くのであった。田舎じみた黒服を着て……ほとんど一口もきくことはなかった。……その孤独感は、ただ異国人の間でだけのことではなかった。生徒の中にもイギリスの娘が何人かいたが……つき合うことをしなかった。またこのブラッセルズの町には、……英人も住んでおり、そうした人々は日曜や祭日には招いてくれもしたが……黙りどおしであり……社交的空気に融けこむことなどは不可能であって、しまいには、その好意ある人々さえも愛想をつかすほどであった。彼女にしても、あるいはそのように人々から放置されることの方に自由を感じたかも知れなかった」(前掲書、五五-五七頁)という。彼女は年とともにますます内に沈潜し、まるで別の世界の住人か誰とも無関係に立っているような感じを、宗族のものにすら与えたようである。このような彼女も、ひとたび人間を相手にしない生活、すなわち自然の中に入ると別人のように生き生きしたといわれる。「岩の間や水ぎわにまるで小児のようにたわむれ……犬を愛したり、野で傷ついた兎や小鳥を助けたり、またそれらに人間にでも対するように話しかけたり……」(同、二七-二八頁)、とにかく人間を相手にしないでいる時だけが、彼女にとって自由に呼吸のできる時であった。 彼女が時代からまったく抽象的に、社会的意識のない生涯を送った主な原因は、この異常なまでに繊細に内向した性格の歪みにあったと思われる。一体どこからこの歪みが来たのか。それをおいたちに求めるなど、いろいろと説明はできるであろうが、大切なことは、彼女がこの歪んだ性格を矯正して、一般的なものに調和するよう直さないで。その特異さを担い切ったということである。彼女とて、一般的なものをあこがれたにちがいない。しかし、彼女の歪みは、一般性回復不能であった。その時、彼女はその異常な歪みを敢然と担ったのである。次の詩は、一八三七年に作ったものの断片である。 強くわれは立ち 怒り、憎み、また侮蔑を忍ぶ。 強くわれは立ち 人間らのわれとの戦いのあとを笑う。 (阿部知二訳) 彼女にとって本質的なことは、その性格が病的に歪んでいたことではなくて、この詩にうたわれているような、歪みを担い切った凛々しさであった。冒頭の詩に彼女みずからいう通り、「抾儒でなかった」点である。そして、一切の問題を神と彼女自身との間だけの問題という形に深めたことである。一八〇〇年代のヨークシャという時代性と地域性を越えて、普遍的、永遠的なものが顕現するまでに、個人という微細な一点に留まったということである。一般性からはみ出た個人を誠実に凝視して、時代の痕跡を留めない、人の人たる限り永遠に妥当する人間の本質を開示したということである。 マルクスは『フォイェルバ″ッハについてのテーゼ』の中で「人間の本質とは、個々の個人にやどる抽象物ではない。人間の本質の現実の姿は、社会的諸関係の総和である」(高田求訳)、といっている。いわゆる人間の本質なるものが、歴史的、社会的諸条件から抽象されて、人の人たる限り存在するものと普通考えられるのに対し、彼は生涯における人間相互の政治的、思想的つながりの中で弁証法的に検討すれば、それは抽象的個人を人間という共通の類でくくった観念に過ぎないと批判するわけである。そして、そういう観念が個人の内部に宿っているものと想定しているのが、たしかに批判されるように、人間の本質といわれているものかも知れない。しかし、そういう理解は、生産労働こそが人間を人間たらしめる決定的なものである、という前提に立ってのことであろう。神の愛を信じる信仰においては、神は無から有を呼び出される神であり、この神に呼びかけられるところに、人間を人間たらしめる決定的な面があるわけであるから、そこにおいては批判される抽象的「個人」というのは、決して歴史的経過を切り捨てて固定された抽象的存在ではなく、むしろ神の前に現実的に存在する人間の唯一の在り方というべきものなのである。「個人」というのは、歴史的、社会的には抽象的存在であるかも知れないが、神の前では現実的、具体的存在なのである。いかなる条件のもとに生きようとも、人は「個人」として、そのままに諸条件を超えて、神に直接し、人間の本質の開示を永遠の相のもとに担っている。 エミリは、たしかに時代を抽象的に生きた。しかし、それは歪んだ性格を誠実に担った、個人に徹した生涯であった。その時、その歪みは昇華して「時代の痕跡をとどめないもの」を示すものとなったのである。性格の歪みは苦痛である、直せるものなら直せばよい。しかし、エミリのように、その歪みが人をまさに神の前の個人にし、永遠なる神との交わりに導くものとなる場合もあるのであって、そこでは歪みもまた絶対性に直接しているという視点がなくてはならない。換言すれば、歪みを負う苦痛が絶対性に対する内面的関係における誠実である、という視点がなくてはならない。そして、その視点において、歪みは相対化されて、単に直さねばならぬものとみなされる窮屈さから解放され、それはそれなりに人間の本質を開示するものとして、はみ出す権利をゆるされる。この相対化の視点を根拠づけるものは、絶対性の内在としての神の愛であろう。 三 信仰と政治 聖徳太子は、十七条の憲法の中で次のように言う。「人皆心有り、心各執れること有り。彼れ是(よみ)むずれば、則ち我れは非(あし)むずる。我れ是むずれば則ち彼れ(あし)むずる。我れ必ずしも聖に非ず、彼れ必ずしも愚に非ず、共に是れ凡夫(ただひと)のみ」。亀井勝一郎氏によれば、これは「太子の人間研究の結語ともいうべき」 (亀井勝一郎『聖徳太子』亀井勝一郎選集第一巻、講談社、一〇四頁)ものであるか、同時に政治にかかわる信仰者の心得として、太子が到達したところであったともいえよう。 推古朝の十三年、太子は当時の政治の中心少治田宮(おわりだのみや)を出て、斑鳩宮に居を移した。太子自身その理由を語らず、人々もこれを異としたと伝えられるが、結局それは、その前年発布された十七条の憲法の精神か、蘇我馬子にふみにじられてゆくのを見て、深く政治に失望したためと思われる。太子は、そのすぐれた道徳的知性のゆえに馬子と妥協することはなかったが、同時に理想主義者が陥りやすい性急な解決の道、つまり蘇我洙伐もしなかった。そして隠遁したのであろう。しかし、この隠遁を、単純に現実からの逃避と考えるべきではない。それは一三年に及ぶ信仰と政治をめぐる太子の苦闘の総決算であった。 太子の仏教との出会いは、父用明天皇を通してであって、純粋に精神のこととして仏教を学んだ。しかし、太子が生きた時代はそれとはまったく異なったかたちで仏教を受けいれていた。仏教が伝来して既に半世紀、皇位継承をめぐって抗争している氏族対立の中にそれは不幸なかたちでまきこまれていた。すなわち、崇仏派と排仏派の出現反目である。用明天皇在位中に、早くも次の皇位について両派が入り乱れて争うのを太子は見た。政治を正すものとして、政治に先立つべき信仰が、政治のための具となって政治に追随しているのである。用明天皇が亡くなったのは太子一三歳の時であるから、信仰と政治の問題は若い太子の心に深く刻まれたに違いない。そしてそれは、一般的な理論の問題としてではなく、蘇我馬子という崇仏派の巨頭との人格的対決を通して、太子一生の問題として深まっていったのである。用明天皇崩御後、馬子は二人の皇子を殺し、崇峻天皇をも暗殺して権力を握った。そして、推古天皇の摂政として立った太子と共に、彼もまた廟堂に立つ身となった。太子にすれば、天皇暗殺者と共に政治を行なうという奇妙な立場に置かれたわけである。したがって摂政就任第一の課題は馬子に対する処置であったろう。それは単に暗殺者処罰の問題というよりは、また氏族専制を正す政治的課題というよりは、太子にとって政治的悪に対する信仰的決断の問題であった。しかし、太子はついに馬子に対して何もしなかった。何故であるか、後世議論の多いところであるが、亀井氏の指摘するように、太子にとって馬子が不可解な人間であったということが最大の原因であったろう。馬子は崇峻天皇暗殺の密議をとげたその同じ月に、法興寺の仏堂と歩廊を熱心に起こしたと伝えられる。一方では殺人を企て、他方では寺院を建立する、これが馬子である。太子の遺族二十三人は、後にことごとく蘇我家によって殺されている。当時最大の崇仏派たる蘇我家は残虐の血の家族であった。おそらく馬子には信仰は文化の政策であり、政治の具であったろう。信仰を貫くための良心の戦い。そういうものはなかったであろう。崇仏と残虐との矛盾に対して何の疑惑も感じない、そのような彼の信仰は、太子にとってまったく不可解というより他なかったにちがいない。謎である以上解かねばならぬ。共に廟堂に立ちつつ太子の目は政治家としての馬子よりは、巨大な謎としてのその人間にそそがれていった。そしてその目はいつしか太子自身に向けられていったようである。というのは、馬子は太子の祖母の弟にあたる。馬子の血は祖母を通して太子の体内をかけめぐっていないという保証はない。暗い血統の一員と自覚された時、馬子との対決は馬子に対する人間凝視から太子自身の人間凝視となった。そして、馬子に押した殺人者の恪印を、自らにも押さねばならぬことに気づいた。かくて、信仰は太子にとって馬子を自らの中に見出す開眼の機縁となった。「共に是れ凡夫」、一七条の憲法にこれを記した時、そこには共に廟堂に立ちながら馬子を見、また自分を見た太子の約一二年間に及ぶ人間凝視があるのである。馬子洙伐という具体的行動に出なかったのは、馬子の軍事的、政治的力が強大であったからでなく、仏教的諦念からでもなく、謎である馬子を謎のままに断じることなく、その不可解さを正視されたからであり、斑鳩宮へ遷居したのは、この正視のはてに「共に是れ凡夫」の世界が見え、その世界を生きようとしたからであろう。「共に是れ凡夫」、それは単に馬子と太子の問題にとどまらない、人間社会そのものを包む事態である。それは、いかなる政治的事態の中にも否定し難く事実であるところの、人間の根源的事態である。そして、この事態への醒めは、太子にとって政治への冷めとなった。遷居は、その冷めであろう。以後一七年間の太子の政治的活動は次第に小さくなってゆく。遷居はたしかに隠遁であった。しかし、それは単に、理想の挫折に基づくものではない。いわんや現実への無関心、逃避のゆえの隠遁ではない。それは、政治の浅さに耐えられない人間の問題の深さに開眼したからであった。「共に是れ凡夫」、それは太子の人間研究の結語であると同時に、政治に対する太子の限界でもあった。有名な片岡山遊行は、この隠遁政治の時代に起こった。それは、片岡山に出かけた際に、飢えた旅人に会い、当時人格として認められなかったその奴婢に、上衣と歌とを与えるという破天荒な行動をしたことであった。蘇我家の専制の下に平和な日々が続いている時、隋との絢爛たる文化交流のあった時、太子の目は人間に注がれていた。馬子も、片岡山の飢えた旅人も、そして太子自身も、共に是れ凡夫であることを見ていた。人々の目が大きな政治的状況にそそがれていた時、この人間を見る目をもった太子は、おのずから政治に対して距離をもたざるを得なかったのであろう。 政治には「共に是れ凡夫」という視点はない。あっては政治にならない。そこにあるのは、抗争する力であり、利害の対立であり、相手を抹殺する仮借なき追究である。そういう世界に「共に是れ凡夫」という目を持ったものは、住むことはできない。政治の世界からいえば、「共に是れ凡夫」とは、現実社会の対立、矛盾を視野に入れない抽象的道徳論と斥けられるであろう。それは、支配階級が好んでふりまわす協調主義であり、現実世界の改革には無力であるのみならず、悪を放任する役割を果たすものといわれる。たしかにそうである。しかし、それにもかかわらず、「共に是れ凡夫」は、端的に人間の事実であることを主張して止まないものがある。太子にとって、それは政治に先立ち、政治を正す信仰の純潔であり、それゆえに政治に対して距離をもったのである。 信仰は政治に対して距離をもたねばならぬ。それは、現実の問題に無関心だからでも、逃避するからでも、階級的な利害からでもない。ただ一点「共に是れ凡夫」を自覚するからである。「凡夫の自覚とは、エゴイズムの自覚だ。人は他人のエゴイズムに対しては容赦ない非難を浴せるが、その非難にひそむ実に激しい己のエゴイズムを沈着に正視するのは稀である。『共に是れ凡夫』とはまさに之が正視の言葉ではなかったろうか」(前掲書、一〇一五頁)。太子の遷居はたしかに隠遁であった。それは政治的には沈黙することであり、そして無力となることであった。その点決して高く評価されるべきことではない。しかし同時に、それが誠実な人間凝視の帰結として、人間の根源的事実を開示するものでもあったことを見落としてはならない。太子の隠遁は、政治の浅さに耐えられない人間の罪と愛の事実に端的である、というべきであろう。 政治・社会の問題を自己の責任として負い、正しい発言と行動を通して見張りの使命を果たしてゆく、というのは正しい。そして教会と社会とのかかわりについてのこの正しさから見れば、隠遁は無責任な逃避として、糾弾されるべきであろう。しかし、隠遁が太子のように、人間凝視の帰結として人生そのものの姿を開示する場合もあるのであって、そこでは、隠遁もまた絶対性に直接しているという視点がなくてはならない。換言すれば、人間疑視の苦痛か、絶対性に対する内面的関係における誠実であるという視点がなくてはならない。そして、その視点において、正しさは相対化され、隠遁も正しさの窮屈から解放されて、それはそれなりに人生そのものの姿を開示するものとして、はみ出す権利をゆるされる。この相対化の視点を根拠づけるものは、絶対性の内在としての神の愛であろう。 四 結 び V・セーレンセンが指摘したように、今日において単一価値の選択「あれか―これか」は現実の抽象であり、諸価値との対決の持続「あれでもない―これでもない」が具体的な現実凝視であるが、更にそれは、価値からの解放「あれでもよい―これでもよい」になるであろう。すなわち、正しい価値が必ず選択されねばならぬ、という窮屈さからの解放である。それは、正しさの否定ではない。正しさを受け入れまいとする我儘でもない。正しさから逃避する臆病でもない。それは、正しさからはみ出ているものにも、それはそれなりに権利かあるということである。このはみ出しに存在の権利を与え、かつはみ出しているゆえに陥りやすい退落の誘惑からそれを守るのは、神の愛に根拠を置く相対化の視点であろう。とにかく、そこにおいて人生はそう窮屈なものではなくなる。得手な道を選んで、誠実にやればよいのである。 本書は、日本キリスト教団京都御幸町教会が、一九七二年以来毎年クリスマスに発行してくださっている、私の断想集を主にして編んだものである。『灰色の断想』『続灰色の断想』『再続灰色の断想』として、それらはすでに、主として教会の関係者に配られていたが、この度このようなかたちで、より多くの方々に読んで頂く機会を与えられた。衷心より有難いことだ、と思っている。巻末に添えた 「今日における愛の問題」は、最初、『聖書と教会』誌(日本キリスト教団出版局刊)の一九七二年六月号に掲載されたものである。 私一人のための神 万国博問題をきっかけに、日本キリスト教団がその体質を烈しく問われ出したのは一九六九年であったか、その動きの中で、「違う、違う」と、問う方に対しても問われる方に対しても、定かなかたちをとらないままに、叫ぶものか私の心にはあった。それに表現を与えようとして、断想を書き出したように思う。本音を吐こうと心定めて、書き出したように思う。定かなかたちをとらないものを、できるだけ損なわないように、そっとそのままにとり出し、かたちを与えることにつとめた結果が、これらの断想である。しかし、だからといってこれらが、その事態に対する私の信仰の主張であるというわけではない。主体をかけた信仰告白、そんなおおげさなものでも、さらさらない。強いて言えば、まあ自画像とでもいったらよいようなものであろうか。 「違う、違う」という叫びは、以前からあった。関西学院大学の神学部に入学して間もない頃、級友の一人に罪に苦しんでいることを話した時、「君の立場は律法主義的で、罪のゆるしの福音への信仰がない」と指摘され、そういうものかと思ったことがあった。また、卒業論文に対し、教授に「教会論がない」と指摘され、そういうものかと思ったこともあった。それらの指摘はいずれも正しく、キリスト教の正しい教理として、なにか権威ある客観的な規準のように迫って来た。だから、罪を深刻に考え過ぎるのは、自意識過剰で不信仰であると思い、また、教会をキリストの体と、とにかく信じようと努めて来た。しかし、そのように思い、そのように努めれば努めるほど、一般的に正しいと認められている教理に、自分を偽って合わせているような無理が、深く心の底に残ったのである。 「違う、違う」という叫びは、何に向かって、どういうふうに叫ぶべきものなのか判らぬままに、問違いなくその頃からあった。たしかに、私のように、自閉症的罪悪感を脱却し得ないのは不信仰であろうし、教会という共同体が問題にならないような信仰は、聖書的信仰ではないと、私も思う。しかし、育った境遇に基づく性格の歪みによるのだろうか、自閉的な、あるいは自虐的な内面的反省を措いては、私の信仰は空疎なのである。こういう歪みを矯正するのが、信仰の力というものかもしれない。しかし。信仰生活二五年にして、なおいかんともしがたいのである。不信仰だと思う。 やがて、こういう回復不能なまでに病的に歪んだ者を、迷える一匹の羊として、そのままに肯定してくださる方こそが、キリストの父なる神であると信じられるようになった。「私は私のままでよい」と私自身を受けとる、それが神を信じるということなのだと思った時、心の中にあった無理が無くなった。客観的正しさなどおそれる必要はなくなった。というよりは、神の前には客観的正しさなるものは、実は初めから存在しなかったのである。全き肯定をされる神のみが、普遍で唯一の客観的実在であり、人間の世界の内にあるものは、正統的信仰といえども、相対的で主観的なものに過ぎない。信仰は、そのような神を信じるものである故に、人は自分の信仰に、普遍性とか客観性とか正しさとかを求める必要はない。ただその主観性と相対性をわきまえておればよいのである。その限度を自覚している限り、どういう信仰を持とうと自由である。神を信じるということは、人間の世界に「これでなくてはならぬ」というものがなく、「あれでもない、これでもない」のであり、その「あれでもない、これでもない」ものが、「あれでもよい、これでもよい」と受け入れられている、そういう世界、こだわりのない、とらわれのない広い世界を生きるということなのだ。そう思えるようになった時、久しく心の中で叫んでいた「違う、違う」が、押しつぶされるべきものではなくて、そっと取り出して、かたちを与えることが許されているものと、考えられるようになった。簡単にいえば、無理をしないで本音を吐いてよろしい、ということである。考えてみれば、何と久しい間、普遍的で客観的な宗教的正しさという幻影におびやかされていたことか。 そして、こういう気持に導かれた時が、たまたま一九六九年、あの混乱した事態のはじまりの年の頃であった。あの事態が、私の「違う、違う」に、かたちをとるよう促したことは事実であるが、私の「違う、違う」は、なにもあの時にはじめて出て来た叫びではないのである。それは、イエス―キリストを信じた若い日に遡ることができる叫びであった。求め、教えられ、信じている信仰に、私自身を任せ切れないのである。信仰を否定しているのではない。むしろ、真面目にそれを肯定している。しかも、自らをそれに委せ切れず、はみ出すのである。最初は、このはみ出しを逃避と思った。わがままであり、そして、誤りであると思った。しかし、やがてこのはみ出しこそ、まさにすぐれて私の問題であり、内面的に限りなく反省してゆく、そして神と出会う場所として、認容されるべき正当な権利を持つものと考えられるようになった。今や私に求められることは、はみ出さないことではなくて、はみ出しに応じて包みたもうている神の愛を、この私一人のための愛を、しっかり生きることである。「違う、違う」は、この私一人のための神の愛が、誰彼なしに与えられる愛一般に、平板化、観念化、抽象化されることへの、抵抗の叫びであった。だから、それは、他者への批判でもなければ、自分の主張でもない。それは、私一人への神の愛を、誰にも手を触れさせず、そっと大切に感謝していたい願いなのである。したがって、その叫びに促されて書いたこれらの断想が、批判や主張であるはずはないのである。それは、信仰告白といってもよいか、それほど大したものでもない。私一人へ注ぎたもう神の愛の下に、私が見て、私が画いた、私の自画像である。それだけのことである。 誰にでもわかるように、私にしかわからないことを 若干の例外はあるが、断想はいずれも、実際に教会で語った毎週の礼拝説教を、できるだけキリスト教用語や表現を避けてまとめ、そして教会週報に載せたものである。 書く時に心がけたことが二つある。その一つは、誰にでもわかるものを書くこと。わかるというのは、内容が理解し易いという意味ではない。ふと立ち止まって人生を考える、そのようなきっかけを持っている、という意味である。信仰に何の関心も持たない人でも、誰もが成程と思って、一寸立ち止まって人生を見直す、そういうものを書きたいと願った。その二は、私にしかわからないものを書くこと。これは、ものを書く人が誰しも味わう、多くの読者にわかってもらおうとする、あの誘惑との戦いではない。それは、私に通じることしか私にはいえないという、基本的な自己認識から逸脱するまいということである。信仰生活約二五年、牧師になって二〇年、ますますはっきりして来たことは、一人の信仰者としても、一人の牧師としても、一人の人間としても、一般的・普遍的なものから、全くはみ出ているということ、迷い出た一匹の羊そのままの自分の発見であった。それはまた、はみ出たものをそのままに包む、イエス―キリストの父なる神の愛の発見でもあった。つまり、「駄目でもよい理由を持った駄目な人間」、これが、私の自己認識の基本なのだ。私にとって、神の愛は、「お前ははみ出ていてもいいのだよ」である。しかし、それは同時に「お前は、自分に通用することしか考えることのできない男なのだよ。一般に語りかけるなど、身の程知らずの傲慢なのだよ」ということでもある。だから、書くことにどれだけの普遍妥当性があるかは問題外のこととして、私にだけ通用し、私にだけわかることを書けばよいのであり、それ以外のことは書いてはならないのである。誰にでもわかるように、私にしかわからないことを書いて、この断想は生まれた。 「ひとり」「ゆっくり」「面白く」は、一九七二年に発行したものに記された見出しであり、「端的に」「美的に」と、「疑う」「仕える」とは、それぞれ一九七三年と一九七四年のものである。それらは、それに含まれている断想を内容的にまとめて現わしているものではない。それらは、その年その年の私の心の中に、定かならぬ姿であったものが、断想を書いているうちに次第にはっきりとかたちをとって来たものである。だから、私の気持としては、その年その年のどの断想にも、その年の見出しが、基本的な調べになっているように思っている。さらに。一五〇の断想のすべてに、三年間に浮かび上がって来た七つの見出しが、強弱濃淡さまざまではあるが、やはり基調として流れているように思っている。だから、大きな見出しに関係なしに、一つ一つの断想を読んで頂きたいと思うと同時に、一つ一つにあまり関わらずに、全体から七つの見出しを読んで頂ければ幸い、とも思っている。これら七つの見出しは、私が私自身に呼びかけてうなづいている、人生の合言葉のようなものである。 淡い交わり 考えてみれば、私の交わっている人々の数は、多くはない。というよりは、むしろ少ない。また、その交わりは、厚く濃いものではない。むしろ、薄く淡い。しかし、そういう淡い交わりの中で、あの人この人のおかげで今日あるという感謝の念は、強い。 高等学校(旧制、大阪府立浪速高等学校)を卒業する直前、事実上休学して、社会事業のポランティアーとして、母子寮で短期間働いたことがある。虚栄心や劣等感に苦しみ、学生生活を続けることに行き詰まっていたのである。父や母に言い難い悲しみを与え、家族に迷惑をかけた。その頃である。大阪府庁の、たしか民生部(局?)に行って、社会事業のボランティアーとしての登録をしたことがある。窓口で受けつけてくれた、年の頃三〇歳位の人が、しげしげと私の顔をみつめて、「浪高?惜しいなあ、卒業してからにしては?うちの部長は浪高出身だから、一度相談してみたら}と、くりかえし、しつこくいってくれたのである。その時の私は、退学そして社会事業と心定めていたので、すぐにその親切を断り、手続きを進めるように促した。そして別れた。その窓口の人との出会いは、それだけである。すっかり忘れていた。ところか数年前、全く突然この人のことを思い出したのである。あの頃の私は、爆弾を抱いているような顔をしていたとよくいわれるが、そのように思いつめている青年を、単に窓口で処理するのでなくて、それでその人の務めは十分果たしているわけであるのに、何とか退学を思いとどまらせ、生きる道をふみはずさせまいと、部長に会わせようと配慮してくれた親切が、全く突然、前後の脈絡なしに思い出されたのである。私は一人目頭を押えて、二〇数年ぶりに気がついた不明を恥じつつ、感謝したことであった。彼の名前は知らない、顔も忘れた。時間にして十分位の出会いであったろうか。こういう人を友人と呼ぶのは、おかしいことかもしれない。しかし、私はそう呼びたい。この人に対して自然に湧いて来た思いこそ、友情の本質ではないかと思うからである。それは、親密さなどとはおよそ関係のない、また取り立てていうほどの強さも特異さもない、ただ静かに湧いてくる平らかに開いた素直な心である。感謝の心である。そして人と人との交わりは、この素直な感謝が自然に湧いてくることに、極まるのではないか。 「親友」、私はこの言葉を好まない。厚く濃く交わって、なおその友情に酔わず、排他的に閉じず、お互いを見る目がくもらず、総じて甘さに流されないほどに、人は決して冷静ではないのである。交わりは淡くなくてはならない。醜さがお互いに見える故に、節度としての距離を保ち、また、弱さがお互いに見える故に、同病相憐れんで交わる、この節度と暖かさを淡さというのであるか、これこそ、交わりにおいて大切な問題であろう。冷淡とか、薄情とかではなくて、人間をよく洞察している故に淡く交わる、そこから平らかに開いた素直な思いが、おのずから湧いてくるのでないか。友は、必ずしも多く持つ必要はない。自然に増えてくるのは、人生の一つの幸いであろうが、少ないことは不幸ではない。また、必ずしも厚く親しく友情を結ぶ必要もない。交わりの最大の問題は、淡さにあるように思う。そして、交わりを淡く持つことにおいて、平らかに開いた素直な心が、特定の人に対してではなく、接するすべての人に対する感謝の念となって、湧いてくるであろう。「お蔭さまで」という言葉は、何気なく平素使っているか、この言葉を、自然にそして真実に、湧き出る言葉として使えるなら、交わりは美しく極まっていると思う。この点において、甚だしく足らざるを覚えつつ、今日までに出会った多くの方々に、感謝をしたい。 このあとがきを書きながら、今日まで導いてくださった日本の、そして外国の先生方、若い日悩む魂を受けとめてくださった教会、そして今日まで、それぞれ十年づつ仕えて来た二つの教会のことを思う。また、あの大阪府庁の民生局の人のような、名前も知らず顔も忘れたが、その出会いに人生を発見させられた数多くの人々を思う。その中には、Hさんのような韓国人もいる。彼は、日本の国策で、無理矢理日本人にさせられたり韓国人にさせられたりしているうちに、ついに無国籍者になり、あんまを生業としながら放浪している。そして、年に一、二度訪ねて来ては、日本がいかに住みよい、良い国であるかを、話してくれるのである。また、京都五条坂下の裏長屋に住むNさんのような、小児麻庫の婦人もいる。彼女は九〇歳を越した祖母を抱えながら、家事一切を足でやっている。そして、こつこつ足で書道に励み、自己研讃を怠らない。また、断想集を読んだからといって、各地からお便りをくださった方々もいる。その殆どは、どうしてこの人の手にあの本が渡ったのだろうかと不思議に思うような、全く未知の人々である。これらすべての人々に、「お蔭さまで」と、申し上げたい。 しかし、誰に対してよりも、特に「お蔭さまで」と言わねばならぬのは父である。父への思いは、七年前に書いた次の文章に尽きている。 ……高校時代、いわゆる左翼的な学生運動にはしり、また事実上休学して一二月程社会事業施設で働いて父を悲しませたことがあった。父はささやかな規模ではあるが建築会社を経営していた。そして経済的に何の苦労もない恵まれた家庭に私は育った。しかし、この「富める者」であるということに対して、どういうわけか私は一種の罪悪感と抱いていたのである。その記憶は小学校の下級生時代にさかのぼることが出来る。そしてこの「富めること」の罪悪感が富める者である父に対して、何かゆるさない気持を持たせたように思う。「商売」、これは私の最も軽蔑した言葉であった。父自身は決して商売の好きな、また上手な人でもなかったと思う。元来は軍人志望であったと聞いたが、商売よりは人生を深くみつめて自分の人格の向上をはかることに熱意を示した誠実な人であり、この点においては生涯、晩年闘病中の十年間も怠ることはなかった。広さよりは深さを求め、量よりも質を大切にし、結果よりも動機を重んじる人で、一種の思想家であった。義理人情にあって、よく人々の世話をみる思いやりの深い人でもあった。古美術を愛し、茶の湯にしたしむと共に、驚く程自由な進歩的な考えの出来る教養豊かな人であった。あえていうならば、私は父ほどの人物に出会ったことがない。父を尊敬し、誇りともした。しかし、「富」をめぐって父に対する気持は素直さを失った。出来るだけ父から離れ、自立しようとはかった。家業を継ぐことをいさぎよしとしない気持が強かった。 いろいろな事情と経過をへて私は信仰を与えられた。学校を終え、はじめての任地が九州に与えられようとした時、いよいよ父から離れうる時が来たと思った。しかしその数年前母を失っていた私は、父の側を離れるべきでないと考えた。そしてすでに二年間牧会実習に行っていた大阪の教会に引き続き奉仕することにしたのである。このことは結果として、父よりの経済的援助をいさぎよしとしない気持を抱きつつ、現実にはそれによってしか生活出来ないという苦しい状態を約十年間私に余儀なくすることとなった。父の援助と、教会の経済的事情に対する父の理解に感謝しつつも、そしてその援助なしには現実には生計の立ち得ないことを承知しながら、父のさしのべてくれることが一つ一つ重荷であった。そしてそれは父への対決の姿勢となった。父を尊敬しながら抵抗した、誇りとしながら批判した。父はめんくらったであろう、理解しがたかったであろう。それは本来父への対決としてではなく。私白身、富を罪悪視しつつも実は富に安住しようとする私白身への戦いとなるべきものであったからである。そしてこの十数年、この戦いに私は敗北しつづけて来た。この敗北を、私一人が傷つくべき敗北とせず、父との対決というかたちで、父の心にも傷を与えたのは、私のずるさであった。…… 親不孝の限りを尽くしたと思う。詑びと共に。かずかずの言い尽くしがたい配慮で包んでくれた父に、「お蔭さまで」と言いたい。 この断想集が発行されるに当って、京都御幸町教会の役員会が示してくださったご厚意を忘れることはできない。全く役員会のお蔭である。記して心より感謝申し上げたい。生来の引っ込み思案のために、発行すると言ったり、止めると言ったり、掴みどころのない優柔不断な私を、常にゆるしてこころよく協力し、発行してくださった。特に、熊谷哲夫氏(質商・金欄緞子製作)に感謝したい。断想を書きはじめて一年半位たった頃から、役員会の中に、発行してはという声があった。しかし、何事にも自信の持てぬ私は、言を左右にして肯じなかったところ、一九七二年九月、氏は断想五〇篇を選び出して私に示し、費用は出させてもらうから、と発行を促された。これが、正篇発行の直接のきっかけとなったわけである。さらに続篇についても、当時すでに肝臓癌で入院中の氏より、促しを受けた。その時も発行する気の全く無かった私は、極めて憂慮すべき病状の中で語られる氏の言葉に、厳粛な思いで従わざるを得なかったのである。続篇発行の約半年後、氏は亡くなられた。再続篇をお渡ししたのは、未亡人に対してであった。 およそ説教らしくない、ひとりよがりの説教を、忍耐強く聞き、それぞれの信仰の糧としてくださる京都御幸町教会の皆さんに、敬意と感謝の念を表させて頂く。この思いは、若い日、未熟な私を迎えて十年間共に歩んでくださった、そして、ここ数年の教団紛争の間に事実上離散してしまった大阪千鳥橋教会の皆さんに対しても、全く変わることはない。 * 本書を熊谷哲夫氏に献げる。亡き父と母とに献げようか、とも思ったが、「熊谷様に献げなさい」と、父に叱られた。私にとって、父は今なお生きている。 * あとがきとしては、長くなり過ぎた。お許しをいただきたいと思う。 一九七五年二月 藤 木 記 ――――――――――――――――――――――――――― 重版にあたって 二十年前、おそるおそる出版した本書が、細々ながらも読者に恵まれ続けて、版を重ねてゆけようとは、全く想像もしないことであった。おそれの念を更に深くすると共に、素直に喜び、感謝している。それにしても、こういう本をどういう方々が読んで下さるのであろうか。私はその読者の存在に、現代の日本の宗教(とくにキリスト教会)への問い掛けを感じている。 本書を出版し続けて下さったヨルダン社の藤野精三社長のご厚意に深く感謝する。特に担当の古家克務氏には大変お世話になった。 一九九五年九月 藤木正三 |