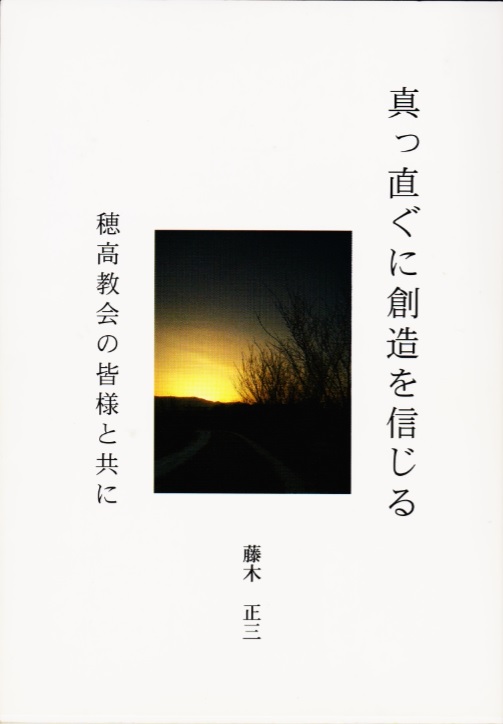
|
目 次 まえがき 「私のキリスト教」 藤木正三 この説教集が《出るまでのいきさつ》については、毛見昇牧師が”あとがき”で書いて下さるだろうと思いますので、私はこの説教集を《出すことを認めるまでのいきさつ》について少し述べて、”まえがき”に代えさせてもらおうと思います。 毛見牧師から説教集を出してよいかとの問い合わせを受けたのは、2007年12月7日でした。応諾の返事をしたのは、年は越さなかったと思いますが、非常にためらった揚句の果ての、優柔不断さ丸出しの恥ずかしいものであったのを覚えています。恐らく毛見牧師は、その返事をどう理解したら良いのか困られたのでないかと思います。しかし、これは何も今回に限ったことではなく、私にとっては若い頃から繰り返している、言わば私の習性とも言える悪い癖なのです。 説教をコピーして配布するとか、テープに採ってダビングして回すとか、そういうことが流行しだした四十年位前から、「そんなこと止めて下さい」「やらせて下さい」の押し問答を、そのたびに私は繰り返して来ました。結果はいつも「承諾」に落ち着くので、押し問答は私にとって《通過儀礼》みたいなものだと笑われる始末で、恥ずかしいことでした。 説教が録音され、書き写されて、一般に公開されることを好まない牧師はいると思います。“礼拝で語られ聴かれて、そこで言葉の出来事として体験されてこそ説教”という神学的立場を強調されるからだと思います。古い例では植村環牧師はそういう方だったそうですが(加藤常昭『自伝的説教論』キリスト新聞社、170頁)、私の場合はそんな真っ当な説教論に基づくものではないのです。では何故そんなに説教集発行に私はためらうのか? その「ためらい」について思うところを述べて、“まえがき”とします。 もちろん最初は漠然としたものでしたが、私は求道の当初から、聖書の与える感動が「私の生命的真実」となること、その一事を願っていたように思います。振り返って見ると、この願いは今も変わりなく一貫してあり、また次第に強くなって来ているように思います。 ところで少し厳しいことを言わせてもらうなら、私の見るところ、日本のプロテスタント教会はこの百数十年、聖書に感動して来ましたが、その感動は教会内でのみ通用する用語で受け止められて、その結果、そのようなものとしては信仰者の思考と言辞と生活の中心になったとしても、感動を与えた《生命》そのものは日本の大気に如何程の痕跡を残しているのでしょうか(清水 氾『躾のきいた美しい文章』書評誌・いのちのことば 1986、4、36頁)。教会の機能は本来、その成員一人一人が、聖書の与える《生命》の感動を各自の生命的真実として生きるためのものであるのに、実際はそうでなかったのではないでしょうか。つまり、正しい教義の確立と、伝道と奉仕に生きる教会の形成の名の下に、《生命》を観念(教会用語)レベルの納得ではなくて、生命レベルの納得で受け取ろうとする一人一人の願いが、正当な扱いを受けて来なかったのではないでしょうか。そして、私が牧師職にありながら、教会に終始違和感を禁じ得なかった大きな一因もそこにあったと思うのです。そういう中で私の考えていたことは、次のようなことでした。 日本の教会でキリスト教の土着化が言われて久しくなります。そしてその努力の一つとして、日本の精神的伝統に受肉した「日本のキリスト教」がしきりに問題とされて来ました。それは極めて意味あることだと、私は思っています。しかし、私は「日本のキリスト教」よりも、聖書の《生命》が「わたしの生命的真実」となる「私のキリスト教」を問題としたいのです。そして、その視点で聖書を読みたい、というよりは、それより他に読みようがない、そう思って来ました。 私が説教でお話しすることは、そういう「それより他に読みようがない」私の聖書の読みに基づいているのです。ですからそれは、当然私にしか通用しないものであり、こじつけという批判に甘んじねばならぬものであり、言わば「私語」でした。私が書いて世に問うたものの大半が「断想」であり、一部「エッセー」であったのは、そういう読みを表現するのに、それらの型が適していたからです。「説教」をそのまま活字にする気は全くなかったのです。 「説教」は私の場合、「公開された独り言」であり、従って、それが活字となり、私から離れた一般の広場で批判にさらされるものとなるのは、正直なところ私は嫌なのです、もっと正直に言えば、怖いのです。私の聖書の読みは、聖書の与える《生命》の感動が「私の生命的真実」になるためには、これしかないものではあっても、こういう風に聖書を読むものだ、というものではそもそもないからです。そんなことを主張する気は初めから毛頭ないのです。ですから、そのまま活字にすることに、私は強い「ためらい」を覚えざるを得ないのです。しかし、良く考えるまでもなく私自身分かっているのですが、その「ためらい」の底には、少しでもお役に立っているのなら、折角の勧めにそのまま素直に従えばよいのに、そうしようとしない、安全地帯に自分を隠しておこうとする頑固なずるさがあるのです。 仏教詩人榎本栄一さんは、その詩集『光明土』の後書きに、「わたしのごとき凡作者はなるべく多く書き残すのが大事で、そしてその選択は読者にお任せ申すのがよろしいと心得ています」と書いておられます。この「お任せ」が、私にはない、出来ない、高慢なのです。 榎本栄一さんは、私の知っている限り、約1500編の詩からなる8冊の詩集を出しておられます。全部読んだわけでもないのに、失礼を顧みず言えば、玉石混淆と言えるかも知れません。しかし、その全部が榎本さんなのです、それをそのままに出しておられる。自分が自分であるための素直さ、勇気、とらわれの無さ、その「心得」は、さすがだと教えられました。榎本栄一さんの詩を最後に一つご紹介しましよう。 世間様献上 お恥ずかしいが 不器用な私がまとめた 昔風の 団子です そのひそみにならつて、私は 穂高教会の皆様献上 お恥ずかしいが 不器用な私かまとめた わたし風の 聖書の読みです 毛見牧師、穂高教会の皆様、故南雲 栄牧師、春日教会の皆様、有り難うございました。穂高教会の礼拝に日本の各地から集まってくださった皆様にも、心より感謝しつつ。 2008年8月31日 藤木 正三(ふじきしようぞう) 1927年 大阪に生まれ、関西学院大学院において神学を学び、牧師となる。 1953年より日本キリスト教団大阪千鳥橋教会、 1965年より同教団京都御幸町教会の担任牧師を勤め、1993年引退する。 現在、日本キリスト教団引退牧師(単立千里山教会に出席)。 本書は、復活之キリスト穂高教会の主日礼拝で語られた、藤木正三先生の説教集です。藤木先生は2001年から2006年まで、六年間穂高教会の招きにお応えくださり、六回礼拝説教のご奉仕をしてくださいました。この六編の説教と、1995年8月、穂高教会新礼拝堂の献堂礼拝での説教を加えて、七編の説教をまとめました。 なお本書中の説教テキスト及び引用聖句のみ言葉は、語られた当時のままとしてあり、口語訳と新共同訳が併用されています。穂高教会では2004年以降、口語訳から新共同訳聖書に切り替えました。時代はこういう過渡期でした。 今回の説教集刊行の準備のために交わした、藤木先生とのメールのやり取りの中で、「今回の企画が《毛見と藤木の共同作業》となることを私は願っておりました。従って、あとがきは大切な意味を持つものと私は実は期待している・・中略・・今日ある君の信仰はどのような歴史を持ち、今後どのようなことを望み見ているのか、或いは、見るべきか、年齢的にも、社会的にも、教会的にも、一つの区切りの時でないのか」と、「あとがき」を書くようにとのお勧めをいただきました。私は「ひるんだ」のですが、確かにこのような機会でもなければ自分の来し方を振り返り、これからを考え、まとめておくことも無いのではないかと思い直し、自分自身にとって「一つの区切り」として、この企画を受け止め、先生のお勧めを受けることにしました。 しかしこれを書きながら、「あとがき」は、精神科医の工藤信夫先生に書いていただくのが良いのでは、という思いが常にありました。藤木先生の信仰に早く(三十一年前)から深く共感を寄せ、教会でも大学でも、全国各地での講演会、セミナーなどでも、その紹介に長年尽力して来られた方だからです。それで迷惑を省みず、「藤木先生への思い」を書いて下さるようにお願いしましたところ、快諾してくださり早々に素晴らしい原稿を寄せてくださいました。そこで「あとがき」のはじめに、工藤先生の寄せてくださいました文章を感謝して用いさせていただきます。 * 「よき出会い」 精神科医 工藤 信夫(くどう のぶお) 言うまでもないことですが、人生を歩むにおいても信仰生活を深めるうえでも、一冊の本、 一人の師との出会いが決定的な働きをすることがあります。 一介の臨床医として、また一キリスト者として、多くの人々の生の困難を、また信仰生活の錯誤を見聞きしてきた私に、三〇代後半で出会った藤木先生の著作とその人となりは正にそういう役割を担ったものでありました。先生の断想を知ったのは、梅光女学院大学(下関)の講演会の帰りであったと記憶します。講演会の後というのは、それなりの疲れを覚えるものですが、気持ちの転換を計るべくチャプレンから何気なく手渡された薄い小冊子を手にして、私は一瞬ドキリとしました。そこに盛られた断想が、今まで見たこともない〈人間洞察〉を含んだものであったからです。新鮮な驚きを覚えた私は、大阪に戻ってすぐに先生の著作を全て探し求め、やがて『信仰による人間疎外』なる本の草稿をもって、その出版の可否を伺うべく京都御幸町教会に出向いたのでした。 それは通常、クリスチャンにとって常識となっていた、教会へ行くことはよいこと、信仰を持つことはよいことという漠然とした考えに一石を投じることになるこの本の出版を、どのようにしたらよいのか考えあぐんでいたからです。つまり当時の私は、無理な信仰生活を強いられたり、この世の組織と何ら変わらない教会組織にはめ込められたため、不自由にされ歪められてきた人々の相談事例に関わってきた者として、心の健康を守り何とか信仰の健全化を計りたいと思いつつも、こうした類の本を出版することに大きなためらいを抱えていたのです。そして、意見を求めても仲々その出版の可否を率直に述べ得ないキリスト者の多くに、それなりのいら立ちを覚えていたのでした。 ところが、不思議な事に藤木先生は、いとも容易にまたきわめて率直に、「私共キリスト者も教会も、指摘されるような多くの誤りを冒しております」と言われたのです。これには驚きました。何らの自己弁護も正当化もされない藤木先生の態度に私は、内心抱いていた”怒り”が静まっていくのを覚えたのです。“ウン、この先生なら信用できる”私はこう思ってこの本の出版を志し、この問題意識はやがて藤木先生との共著『福音はとどいていますか』(ヨルダン社)に発展していったのでした。 今思うと私かそこで経験したことは、きわめて素朴に、また率直に自らの非を認めるいさぎよさ、真理に謙虚にうずくまりなさる先生の人生態度そのものでした。 藤木先生の最近の御著書に次のような表現があります。「人間誰だって、程度の差こそあれ正しくないことを皆して生きています。これは仕様がないことです。問題はそれが問われた時です。素直でないことが罪なのです。」(『神の指が動く』59頁) 私は、この《生涯一病人》としての自覚を失わず絶えず自らを問い、自らを照らす姿勢が藤木先生の信仰の特質と理解しております。そして〈照らしを受け続ける〉、実はこれがキリスト者に、生涯求められる信仰の基本姿勢でないでしょうか。〈罪を照らす光はまた癒す光でもある〉 (ジョージ・フォックス) 藤木先生の著作で、多くの人々がキリスト教的縛りから解放されるのは、このゆえであるように思われます。以下の書評は私か先生の著作『神の指が動く』に関して記したものですが、この間の消息をよく説明するもののように思われます。 評者はキリスト教主義の病院における精神科臨床を通して、はからずも三〇年近く今日のキリスト教界における人間理解の乏しさ、福音理解の浅さ、粗雑な伝道にもとずく多くの蹟き、トラウマ(心的外傷)の相談事例に関わることとなり、1990年から年一度、軽井沢でこうした方々のためのセミナーを開催してきたが、その参加者の殆どが何らかの形で藤木先生の著作に励まされていた。つまり、参加者の多くは人づてに、先生のこれまでの著作『神の風景』『灰色の断想』『福音はとどいていますか』(以上ヨルダン社)、『この光にふれたら』(教団出版局)、『系図のないもの』(近代文芸社)などを読み、先生の深い納得性に満ちた独自な聖書理解に慰めや励ましを得て、もう一度キリスト教信仰や教会に留まろうと決心した方々であった。そしてこの事情は、私か出会った海外の日本人教会の人々(ロンドンやシンガポール)においても同様であった。 藤木先生は、ご自身が語られる聖書理解を終始”聖書的独白”であり、決して説教ではないと言われるが、きわめて個人的独白と思われる。その視点が不思議と私共を「キリスト教という縛りから開放し、確かな自由へ導く力がある」(ある若い牧師のことば)。先生の主張をそっと心の底に留めて、静かなるまた確かな信仰生活を続けている方々は全国各地に点在しているはずである。 さて本書(評書『神の指が動く』のこと―あとがき筆者)は〈藁(わら)をもつかむ信仰〉 〈イエスの過度と人の身勝手〉 〈神との関係〉 〈罪びと一列〉 〈神の完全・人の完全〉 〈小さい声で「今が一番いい」〉 〈限定的肯定〉など十の聖書的談話が収録されているが、いずれにも見られる聖書解釈は、私共に神を信じるということは一体いかなることであっだのかの原点を知らしめこれだったら私も主イエスを信じられるという安心感に導く。 例えば、〈藁(わら)をもつかむ信仰〉の中に次のような記述がある。「服にでも触れればいやしていただける」(マルコ5:28)と思った十二年間長血を患った女の信仰は単純というか、素朴というか、ご利益的で魔術的といいましょうか、間違いなく言えることは、自分の罪を認め、神の子イエス・キリストの十字架と復活の罪のあがないを信じ、悔い改めてその主に委ねて功ないままに救われる、そういった教会が語る教理的に正しいと私たちの思っている信仰とは、どうも違うということです。……中略……わたしならばそれはキリスト教の信仰じゃないと多分言うでしょう。 しかし、イエスはそんなずるい身勝手な迷惑なそれでも信仰かと言われたら一言も返せないようなものを、藁をもつかむ一念において「あなたの信仰があなたを救った」と言ってほめて下さったのです。(評書29頁) 実の所、私たちの信仰生活の実際は迷いがちであり、信じ切れないで苦労しているのではないだろうか。そしてしばしば教会は、そうした人々にいわゆる神学的、教理的に模範的な<すばらしい信仰>など提示して律法主義的に人を切り捨てる所があったのではないだろうか。 (以下略) 以上のような事柄から、今の私が理解し得た藤木先生の信仰理解また特質は次のようなものである。 1、説得、納得性に富む <この人の言うキリスト教だったら私も信じられる>という安心感、広がり。 2、教えではなく生への思索 「宗教は、生かされているという存在の事実に気づき、生かされているというセンスで生きる ことを促していく生への思索なのです。もしこの生への思索が宗教からなくなれば、宗教は思弁的となり、教えとなり、その宗教は律法的となり、党派的となり、そして必ず人間を疎 外し、人間を抑圧するものになるでしょう。」(『神の指が動く』10頁) 3、信仰者の自由 スイスの精神科医P・トゥルニエの古典的名著『人生の四季』(ヨルダン社)の中に、〈キリスト教は、人間を解放するものか、抑圧するものか〉という魅力的な章がありますが、そ の中で博士は、当時のヨーロッパ(1950年代)を支配していたのはキリスト教に形を借 りた”律法主義“つまり教えであることに言及しております。私の臨床医としての三〇年間、そしてキリスト教との闘いは”must should”思考、つまり”こうあらねば“という”ねば志向”との戦いでもあったといえましょう。この点藤木先生は、教えに留まるキリスト教の限界を早くから感じ取って、警鐘を鳴らして来られた方にちがいありません。この点では臨床医の視点と藤木先生の視点に共通するテーマを感じてしまいます。ともあれ日本の宣教が”教えのレベル”に留まる限り”信仰による人間疎外”はこれからも続くでありましようし、藤木先生のご本は心ある人々の心を解放し続けるに違いありません。よき出会いをお与え下さった主に感謝! * 「あとがき」としてはこれで十分、とも思うのですが、「まえがき」に、「この説教集が《出 るまでのいきさつ》については、毛見昇牧師が”あとがき”で書いて下さるだろうと思いますので」、とありますので、拙いながら、前述しました藤木先生のお勧めに従い、「これまでの私の歩み」を記して「この説教集が出るまでのいきさつ」とします。 藤木正三先生と出会い、そして今、穂高教会での説教集が刊行されるに当たり、私はローマの信徒への手紙にあるパウロの言葉を、畏れと感謝の心を抱きつつ思い起こしています。 「ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか。だれが、神の定めを究め尽くし、神の道を理解し尽せよう。すべてのものは、神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように、アーメン」(11章33節、36節)。 私が信仰を育てられた教会は、現在私が奉仕をしている復活之キリスト穂高教会です。幼い頃は母に連れられ、小学生からは姉と一緒に教会に通いました。その頃の私は自分から積極的に教会に行くというよりも、行かないと母に叱られますので、友達と遊びたいのを我慢して仕方なく通っていたのです。 未だ忘れ得ぬエピソードがあります。教会学校でのことですが、担当の先生がお話されている間、私は落ちつきなく、周りの子どもたちを巻き込んで騒いでおりました。その時先生が「・・・に行きたい人?」、と私たちに質問されたのです。その質問の内容も分からないまま(騒いでいたものですから)、私は「はい」と言って思いっきり手を上げました。その場に居合わせた子どもたちは途端に爆笑、ただ私一人が手を上げてぽかんとしていました。先生は「地獄に行きたい人」と言われたのでした。私が騒ぐことが気に障られたのでしょうか。戒めの意味を込め、私が反省することを期待し、先生はそう尋ねられたのかもしれません。ところが私はその期待を裏切るかのように、教会学校の生徒の中でただ一人、威勢よく堂々と「地獄行き」を志願したのです。そして牧師になりました。 今考えてみますと、神様が「地獄行き」を志願した愚か者を憐れんでくださったのでしょうか。それとも、人間的に考えれば地獄のような「十字架の主」に従わせてくださったのでしょうか。いずれにせよ何か暗示的な出来事であったと思います。 母の怒りを恐れ仕方なく通っていたとはいえ、私の内に少しずつ信仰が芽生えていきました。穂高教会が属している復活之キリスト教団は、聖書理解においてはファンダメンタリスティック(根本主義的)で、聖書の言葉をそのまま信じるようにと導かれ、聖霊の働きが強調され、また「きよめ派」の敬虔主義の影響も強い群れでした。そういう信仰の中で育てられた私は、実に単純に、良く言えば素直に神を信じていたと思います。「神はいるかいないか」などと考えたこともなく、「神はいる」という前提しか私にはありませんでした。困ったことがあると何でも神様に祈り求めました。 「地獄行き」志願と共に、忘れ得ぬエピソードがあります。 ある時友達と近所の空き地で草野球をやっていて、ボールを無くしてしまったことがありました。当時は貴重なボールであり、皆で一生懸命捜しましたが見つかりません。黄昏時となり、あきらめてもう家に帰ろうと、皆帰りはじめました。しかし私はあきらめきれなかったのです。無くしたボールは私のものだったからです。帰って行く皆の背中を見つめながら、私は空き地の真ん中でお祈りを始めました。「神様ボールはどこですか。どうかボールを返してください」、とそんなふうに祈ったと思います。そして目を開けてみると、私の足元にボールが転がっているではありませんか。私は驚きと喜びでボールをつかむと帰って行く友達に向かって「おーいボールが出てきたよう!」と大きな声で叫んで追いかけて行きました。大人になってこの出来事を思い出した時、実はあれは友達の誰かがボールを隠しており、持って帰ろうとしたが、私があきらめ悪くお祈りを始めたので、うしろめたくなってボールを私の足元に投げ返したのではなかったか、と思い至ったのですが、あの時の私にとってこの出来事は、神はおられるのだとの思いを更に堅くさせるものとなりました。 「イエス・キリストの十字架の死は、私の罪の贖いの死であり、この恵みによって救われる」と信じて中学一年で洗礼を受けました。しかしそれは迷い悩んだ揚句に到達した深い信仰的自覚を伴うものではありませんでした。思春期の頃、無意識のうちにもがいていたこともあったと思いますが、礼拝を守りつつも、私は信仰とは裏腹な行動を繰り返しておりました。 中学生の時、拝礼こそしませんでしたが、穂高神社のお舟祭りのお囃子に参加し、牧師夫人を嘆かせました。また高校時代はSL撮影のために友人と北海道まで出かけたり、遊びと趣味の資金稼ぎのために、勉強そっちのけで肉体労働のアルバイトに精を出したりもしました。更にその頃の私は作家北杜夫の『どくとるマンボウ青春記』の影響を受けてバンカラをきどり、わざと学生帽をぼろぼろにしてかぶり、腰に手ぬぐいぶら下げて、真冬でも下駄履きで学校に登校したりしていました。硬派を自称し、期末試験の日に景気付けだと称して、家で日本酒を一杯引っかけて学校に出かけたこともあります(マスクをしていきましたが)。気に入らない授業だと学校を抜け出しさぼることもしました。 私の生活は、教会から期待される、自覚的クリスチャン像とはほど遠いものがありました。クリスチャン=良い子というイメージや、母親に対する反発もあったのかもしれませんが、礼拝を守り、聖書を読みながらも、毎日の生活は信仰とは関係なく、自分の思いのままに過ごしていたのです。 不思議なことに、そんな私の行動に対して母は何も言いませんでしたし、むしろ面白がって見ていたふしがあります。また牧師先生も何も言われませんでした。とにかく礼拝を守っているから大丈夫、若い頃に無茶をするのは当たり前、ぐらいに受け止めてくださったのでしょうか。そのことを思い出します時、穂高教会は、根本主義的熱心と敬虔な信仰にありかちな頑迷さ、偏狭や独善性はあまり感じられない教会だったなあと思うのです。その当時の牧師であった岩田徳兵衛先生の説教は「人や現象ではなく、神を仰ぎ見よ」と厳しく信仰を問うものであり、聞くたびに心にこたえるものでした。しかし先生は、いちいち信徒の生活に口を出すようなことはされませんでした。信徒ひとりひとりの問題や課題を覚えて心配し、熱心に祈りを捧げながら裁くことなく神にゆだね、忍耐を持って見守っている、というのが、先生の牧会スタイルだったように思います。神を畏れ、信仰的愛によって、粘り強く信徒を導いてくださった、偉大な先生でありました。 私が次第に信仰を生き方の問題として自覚化するようになったのは、大学浪人時代のことでありました。 浪人時代、同じ境遇の友人たちが松本の予備校に通う中で、私は「自宅浪人」の道を選び、 ひとり隣町の図書館に自転車で通いながら、受験勉強に励みました。そんな孤立無援とも言える状態だったせいでしょうか、この時期の私は、敬虔な信仰から見れば放らつとも言える生活を離れ、受験を控えているにも関わらず、日曜礼拝はもちろんのこと、水曜日と金曜日の二回あった祈りの会にまで出席し、さらに毎日夜寝る前に聖書を読み、その感想や一日の反省をノートに記しておりました。将来が見えず、考え始めると震え出すような不安を抱えて、必死に神にすがりついた、ということだったのでしょうか、それは空前絶後の克己的な日々でありました。この浪人時代に「牧師になろう」との思いが与えられていったのです。 高校卒業時に関東地方のある大学に合格していたにもかかわらず、進学せず浪人の道を選びました。しかしその時はまだ「牧師になろう」という思いはかけらもありませんでした。私はただもう少し受験勉強をして、本当に自分の行きたい大学に行こうと思っただけなのです。ところが浪人時代も夏を過ぎた頃、私の内に「誰か牧師先生を助けてくれたら良いのに」という思いがわき起こってきました。高齢となりながらも教会や教団内の様々な問題を担っていた岩田先生のご苦労を知り、そう思ったのでした。その思いがある日「助けるのはおまえではないか」に変化したのです。まったく考えてもみませんでした。突然そういう思いが与えられたのです。それは信仰心というよりは「義を見てせざるは勇なきなり」といった義侠心的発想だったかもしれません。しかし、私は「助けるのはお前ではないか」との心のささやきが気になり、ついに迷い悩んだ揚句、神を試すことにしたのです。神を試してはならないのですが、しかし本当に自分が牧師を助けるべきかどうか確信を持てなかった私は、まことに単純な発想ですが、神学部に合格したら、この思いを神の導き、召命と信じようと決めました。 私は神学部のある大学を調べ、その中に一つだけ牧師の推薦状を必要としない大学があることを知りました。それが同志社神学部だったのです。私は「これだ」と思いました。岩田先生には、自分に芽生えた気持ちは何も話しておりませんでしたし、何よりも牧師になることを表明し、受験して不合格だったら格好がつかないと考えたからです。私は秘かに神学部を受けることにし、推薦状の必要のない同志社神学部を受験したのです。結局すべり止めに落ち、同志社神学部に合格しました。 岩田先生に合格を知らせると驚かれていました。もし事前に知っておられたら、もっと違う神学校を紹介して下さったのかも知れません。しかし私の決めたことを尊重してくださったと思うのですが、岩田先生は、同志社神学部については何も言われませんでした。そして「大学へ行けば色々あると思うが『すべてはイエス様のため』、と受け止めながら大学生活を送るように」と励ましてくださいました。この言葉は後日私を支えてくれることになります。こうして私は1976年4月同志社神学部に入学したのです。 今考えると何もかも無知であったと思います。同志社神学部がどういうところであるか、何も知らなかったのです。大学を目指していたこともあり、神学部のある大学を受けただけなのです。 修学旅行で数日滞在したことがある京都には、何となく親しみを感じていましたが、実際は縁もゆかりもない街でした。知り合いは誰一人おらず、知っている場所は清水寺と金閣寺と銀閣寺ぐらいのものでした。私は東山二条にある日蓮宗の寺が、その境内に経営していた学生下宿を住まいとし(何故かそこが京都らしく感じられ気に入ったのです)、その頃まだ走っていた市電に乗り大学に通いはじめました。初めてのクラスで同級生たちの自己紹介を聞いていますと、皆自信あり気に堂々としており、鋭い問題意識を抱いている賢そうな人たちばかりに見え、気後れを感じました。 講義が始まりました。神学概論という入学当初に学ぶ講義では、いきなり「旧新約聖書全巻の書名を書け」というテストが課されました。私にとってそれは楽な課題でした。「創、出、レビ、民、申命記・・」と『鉄道唱歌』による『聖書数え歌』を、教会学校で覚えさせられていたからです。しかし聖書のことはいくらか知っていても、神学は何もわかりませんでした。 同志社大学神学部は組合派(会衆派)の流れを汲み、私が育ってきた敬虔主義的信仰とはだいぶ趣が違っておりました。そこに集まっている学生や教授たちは皆個性的で、主体性や自由が重んじられ、「何でもあり」の空気が漂っておりました。神学部自治会の委員たちは黒ヘルメットを被り、反対勢力と小競合いを繰り返していました。入学早々新入生歓迎コンパが大学近くの料理屋で行われたのですが、飲めや歌えやの大宴会となり、某教授が「湯の町エレジー」を熱唱したことと、先生方が学生のためにご飯とお汁をよそってくれたことを覚えています。私はそんな神学部の雰囲気に、いちいち驚かされたのですが、親しみも感じました。私の内にいるもう一人の自分がいたく刺激されたからです。 前述したように、小さい頃から教会に通い、礼拝を守り、イエス様の十字架の贖いに感動し洗礼も受けたのです。しかし一方で信仰とは矛盾するような生活を過ごしていた、本来の勝手気侭な自分が刺激されたのでしょう。「クリスチャンらしくなければ」という、もう一人の自分との葛藤はありましたが、自由な雰囲気の同志社神学部が、私には好ましく感じられたのです。 一方神学の学びにおいてはつまずきの連続でした。それは自由主義的でアカデミックな学究的神学でした。素朴な聖書の読みしか知らず、哲学的素養も論理的思考も希薄な私でしたから、その講義は衝撃的であり難解なものでした。草野球しか経験のない者が、いきなり大リーグのバッターボックスに立ったようなものです。自分はついて行けるだろうかと不安を抱えつつ、自分なりに何とか理解しようと努力しました。しかし「様式史、伝承史、編集史」と言った、歴史批評的研究方法が縦横に駆使された聖書学や、教義学のシュライエルマッハーの講義などを受けるにつれ、次第に自分の信仰を全否定されているように感じ始めたのです。これまでの自分の信仰は何であったのかという自問が始まりました。それまで聖書の言葉はそのまま全部本当のこと、歴史的事実であって、書かれている通りに信ずべきことだ、と教えられ信じてきたものが、そうではなさそうだと分かり、自分の信仰の前提に疑問が生じたのですから大変です。私にとってそれは驚愕の現実でした。神学部の雰囲気は好ましくても、私は次第に自分の信仰も召命の確信も、もろく崩れて行くのを感じ、精神的な空虚さに一ヶ月以上も講義に出られず、下宿に引きこもっていたりもしました。 そんな私を支えてくれたものの一つが、前述した岩田先生のお言葉でした。私は信仰の動揺の中で、そのお言葉を思い起こし気づかされたのです。「(新約)聖書よりも前に教会があり、そして教会よりも前にイエスがおられたのだ。イエスあってこその教会であり聖書なのだ」と。だから教会の在り方や聖書の受け止め方は多様であっても、要は「イエス様のために」学び生きることが大切だと、稚拙で飛躍的な論理ですが、その時は、そう自分に言い聞かせたのです。 またもう一つ私を支えてくれたのは、京都御幸町教会との出会いでした。 神学部の先輩であるAさんと、たまたま知り合いになったことがきっかけとなり、このAさんに誘われて京都御幸町教会の礼拝に出席するようになりました。 初めて御幸町教会の礼拝に出席した時、歴史を感じさせる赤レンガの礼拝堂と、その中で守られている礼拝の厳粛さに圧倒されました。牧師は藤木正三先生でした。 京都御幸町教会には学生寮がありました。礼拝堂に隣接する吹き抜けの講堂の二階部分にそれはあり、寮生が三人寄宿していました。私を御幸町教会に導いてくれた同志社神学部のAさん、立命館経済学部のYさん、京大工学部のNさんです。これら寮生たちとの交流は、慣れない環境での緊張を強いられていた京都での生活に、いくらかの余裕を与えてくれました。信仰的動揺や、克己的な日々を送り続けた浪人時代の反動があったのかもしれませんが、何よりも生来の怠け癖のために、朝起きることが出来ず、なかなか礼拝に出席できませんでした。しかしそんな時も日曜の午後には寮生たちに会うため御幸町教会に出かけたものです。 二回生となる時、私はNさんと入れ替わるように、御幸町教会の学生寮に入寮しました。その時寮生と藤木先生との間に議論が巻き起こったようです。すっかり親しくなった寮生たちは、私の入寮を積極的に賛成してくれたのですが、藤木先生は、私が一年間で九回しか礼拝に出席していないことに、懸念を表明されたのでした。もっともな話しです。その時寮生たちがこう言って先生を説得してくれたそうです。「先生、だからこそあいつを寮に入れなければなりません」。先生も「それもそうだ」と思われたらしく、私は御幸町教会学生寮に入寮を許されたのです。 教会寮での生活は「貧しいながらも楽しいわが家」の日々でありました。寮生は妙に気が い、後から加わることになる神学部の後輩H君との交流も含めて、実にのびのびと身勝手に、思い出すと恥ずかしく、ばかばかしくも懐かしく、そしてせつない思い出に満ちています。 三十二年目の告白ですが、寮の各部屋の前の通路を掃除するようにと藤木先生から注意された時、私たち寮生は、「ほんなら掃除したろか。うるそうてかなわんさかい」と、通路のごみを講堂の床に掃き落としました。その講堂の床は藤木先生が掃除をされていたのです。 知られるとまずいことを色々しでかしていた私たちは、いつもうしろめたい思いを抱えており、時々連絡用の黒板に「一寸来てください。SF」(SFは藤木先生のイニシャル)と書かれておりますと、「ついにばれたか」と恐る恐る先生のところに行ったものでした。 御幸町教会の皆様は温かく寮生たちを見守ってくださいました。そこには、「自分が自分として受け入れられている安心感」、がありました。個人的にお家に招いてくださり、食事をご馳走してくれた方もありました。教会の雰囲気は同志社とは少し違い、メソジスト教会の流れらしく、穏健で平和的でありました。そのような居心地の良い環境の中で私は支えられ、落ち着いて自分の信仰を見つめ直していくようになりました。 寮の規則は二つだけでした。礼拝を守ることと午後十一時の門限です。おかげで私は毎週日曜日の礼拝に欠かさず出席し、藤木先生の説教を聴く者とされたのです。門限はあって無きが如きものでしたが・… 当初、先生の説教に対する印象は「ずいぶん地味だが、きっちりとした説教だなあ」というものでした。先生は理路整然とした説教の完全原稿を用意し、それを淡々と読み上げるという仕方で説教を語られました。夜型生活となっていた私は、当初説教が始まるとすぐにこっくり、こっくりしたものです。しかし、一年、二年と、その語られていく言葉に耳を澄ませてみると、考えさせられることが多々あり、同時に納得と安心を与えられ「楽になる」不思議な説教でありました。 それは工藤信夫先生が前掲の文章で適切に提示してくださったように、「教えではなく、生かされている気づきへ招く生の思索」として、「納得と説得性による受容体験を伴う安心感」として、「ねば思考からの解放」として、私の心を揺さぶるものでした。 藤木先生ご自身が言われていることですが、「教会用語はなるべく用いないで、誰にでもわかるように、しかし自分にしかわからないことを語る」、この困難と思われる課題のために、ずいぶん長い時間をかけて、先生は説教を用意されていたようです。教会学校の中高科の夏期キャンプで、私たちがわいわいと騒いでいる中、藤木先生がお一人部屋の隅でノートを広げ、説教の構想を練っておられる姿には近寄りがたいものがありました。時には「神などいるとも思えませんが・・」、などという大胆な言葉に、ひっくり返りそうになったこともありましたが、次第に先生の考え抜かれた誠実な説教を通して、聖書、信仰、キリスト教、教会に対する再吟味の思いが深められていきました。 神学部での学びや、甚だ不十分な理解ではありますが、興味の赴くままに読んだ、キルケゴールやバルトにおける「神と人間(時間と永遠)の無限の質的差異」という信仰理解、ブルトマンの「世界史と実存史」の分離、「非神話化」による「実存論的解釈」という聖書理解、またティーリケ、荒井献、田川健三等の著書を通し、宗教や根本主義の問題、聖書、福音、信仰、史的イエスの問題などについて考えさせられました。しかし何と言っても、私にとって本当に必要だった信仰的養いは、藤木先生の説教を通して与えられたと思います。私か京都に行ったのはこのためだったのだ、と今思わされています。 私はこの養いの中で、次第に根本主義的な聖書理解の呪縛から解き放たれていきました。それは自分の信仰が相対化されていった出来事だったと思います。「自分の信仰こそキリスト教である」との自己絶対化の思い込みが打ち砕かれていったのです。 《やがて、こういう回復不能なまでに病的に歪んだ者を、迷える一匹の羊として、そのままに肯定してくださる方こそが、キリストの父なる神であると信じられるようになった。〃私は私のままでよい”と私自身を受けとる、それが神を信じるということなのだと思った時、心の中にあった無理が無くなった。客観的正しさなどおそれる必要はなくなった。というよりは、神の前には客観的正しさなるものは、実は初めから存在しなかったのである。全き肯定をされる神のみが、普遍で唯一の客観的実在であり、人間の世界の内にあるものは、正統的信仰といえども、相対的で主観的なものに過ぎない。信仰は、そのような神を信じるものである故に、人は自分の信仰に、普遍性とか客観性とか正しさを求める必要はない。ただその主観性と相対性をわきまえておればよいのである。その限度を自覚している限り、どういう信仰を持とうと自由である。神を信じるということは、人間の世界にご」れでなくてはならぬ”というものがなく、”あれでもない、これでもない”のであり、その”あれでもない、これでもない”ものが”あれでもよい、これでもよい”と受け入れられている、そういう世界、こだわりのない、とらわれのない広い世界を生きると言うことなのだ。・・・》 (傍線あとがき筆者) これは藤木先生の御著書『純粋と微笑 沈黙と愛のパンセ』(後に『灰色の断想』と改題) の一節です。記憶が定かではありませんが、大学生活の後半だったよ思います。これを読んだ時、私は京都にやって来て自分の内面に起こったことが、ここに言い表されていると感じました。 自分の内に絶対的なものとして君臨していた、根本主義的聖書理解に基づく信仰もまた、「普遍で唯一の客観的実在」である「全き肯定をされる神」の前では、まことに乏しく、欠けに満ちた、不完全な信仰に過ぎないこと。自分は全き肯定をされる愛なる神ではなくて、「自分の信仰」を絶対化していた、とその過ちに気づかされ、これを相対化され「これでもない」と、その絶対化(自己神化)の愚かさ危うさから救われたのです。そして同時に、その主観性、相対性をわきまえ知らされたことによって、私に与えられ、穂高教会で養われた、単純素朴な信仰を否定するのではなく、むしろ「私のイエス」として「これでもよい」と、これを受け止め直してゆけばよいことも、また教えられたのです。 それ故に、私は大学を卒業した後、復活之キリスト教団に献身しました。 献身後およそ三年間は、学生時代とは隔絶した環境の中で、祈りと学びと作業による、修道的とも言える生活を送りました。そこにもまた当然迷いがあり、葛藤があり、苦しみがありましたが、京都において与えられた、「絶対的なる神の愛による相対化の視点」に支えられて、「主の前に静まる」修練と、私に最も足りない「忍耐」を学んだ、貴重な三年間であったと思います。お陰様で復活之キリスト教団としては、ちょっと風変わりな私も受け入れていただき、母教会である穂高教会へと遣わされ、今日にいたっております。 今私は、穂高教会の皆様と共に、この群れが、「私に注がれている神の愛=私のイエス」とそれぞれに出会い、そのようにひとりびとりに「その人をその人として」出会ってくださる、神様の愛だけを絶対のものとして、あまり互いの違いにこだわらず、違うところを裁き合わず、むしろ互いに自らの被造性とその限界をわきまえながら、足りないところを補い合い、認め合い、赦し合って、「寄せ鍋」のごとく、いろんなものがいることによって、良い味を出していく群れとして、「おおらかに、広く」、この地に在り続けてゆければと願っています。 何よりも先ず、私自身がこれからも、主の愛の光に照らされて、人ではなく自分をこそ問う、藤木先生が言われる「自己添削:これでもない」を重ねつつ、「私のイエス:これでもよい」との出会いを繰り返し、与えられました務めを「迷い悩みつつ」も果たしたいと願うものです。そのためにも、藤木先生の説教を聴き、これを残したいと願ったのでありました。 京都を去る時、藤木先生は、「牧師の権威は君臨する権威ではなく、仕える権威です。牧師は仕えることに徹する一信徒であります。仕えきれない自分にどうぞ誠実に迷うて下さい]、とのはなむけの言葉を贈ってくださいました。その言葉を胸に秘め、私は心のうちに「さらば京都、さらば御幸町教会」、と別れを告げました。その後、御幸町青年会の面々が、夏の合宿と称して穂高に遊びに来たり、先生の娘さんや後輩の寮生H君の結婚式のため京都に出かけたりと、細々ながら御幸町教会とのつながりがありましたが、現実の牧会生活に追われ、京都での生活は、次第に遠い過去の良き思い出となりつつありました。 そんな時、私と交代するかたちで教会寮を出たNさんが、ご家族と共に穂高に移住して来られたことから、藤木先生と時々連絡を取り合うようになりました。 更に、独身生活に疲れを感じ、誰か良い人がいたら結婚しようと、魚釣りのまき餌のごとく、友人知人を通じて全国に私の写真をばらまいたところ、ぱくりと食いついて? くれたのが、御幸町教会で青年会活動を共にした中島康子(妻)でした。彼女とは、京都教区の教会青年会ソフトボール大会で、ピッチャー(私)とキャッチャー(妻)のバッテリーを組んだことがあるのですが、女だてらにキャッチャーを志願する「変な奴」、とその時は思っておりました。それが本当の夫婦になるとは。 このことによって再び京都御幸町教会が近くなりました。婦人会の皆様は二度も穂高を訪ねてくださいました。新教会堂建設の時には多くの御幸町教会の皆様が、献金を献げてくださいました。 また思いもかけず、藤木先生のご紹介で、新礼拝堂が『信徒の友』に掲載されました。その後も藤木先生を知る方々が、穂高の地に何人もいることを知り、驚かされました。これらの方々は、工藤信夫先生のセミナーを通し、藤木先生をお知りになったのでした。その工藤先生が、突然穂高教会を訪問してくださり、驚かされたこともありました。かねてよりその御著書を通して、土藤先生は、藤木先生と似たような問題意識を持っておられる方、と感じておりましたが、もうずいぶん前から、藤木先生と関わっておられたことを後で知り、「なるほど」、と納得させられました。 そして藤木先生は、献堂礼拝、更に六年続いて礼拝説教のご奉仕をしてくださり、静かに深く、私たちの信仰と人生に、光を投げかけてくださいました。 これをそのままにしておくのは惜しいと、役員会で説教集の刊行が決議されました。 これらはすべて、「さらば」、と別れを告げた私が、予想も願いもしない、「まさか」、の出来事でありました。 「よくぞここまで」と思います。もちろんそれは「自分がよくやった」と言うことではなく、「神様の憐れみによる導き」、を感じての感慨です。 「よくぞここまで」・・・十字架の愛と忍耐によって導いてくださった主と、今日まで、様々な人生と生活の場面で出会った、あの人、この人によって、赦され、支えられてきた自分を、今思わされています。 「ああ、神の富と知恵と知識のなんと深いことか’だれが、神の定めを究め尽くし、神の道を理解し尽せよう。…すべてのものは、神から出て、神によって保たれ、神に向かっているのです。栄光が神に永遠にありますように、アーメン」。 ・・・これが今回の説教集刊行のいきさつであります。 最後になりましたが、三十三年前の出会いより今日まで、勝手に「不肖の弟子」を名乗っている私と、大きな心で関わり続けてくださり、この説教集刊行にあたりましては、これをお許しくださると共に、手取り足取り、校正、編集にご協力くださいました藤木正三先生、和子夫人に、心より感謝申し上げます。 藤木先生の信仰理解のために、心のこもつた原稿を寄せてくださいました工藤信夫先生、原稿入力にご協力くださいました奥村純子様、『信徒の友』に掲載された、「こんな私でも天国に行けるのでしょうか?」の転載を、こころよくお認めくださいました、日本基督教団出版局の伊東正道様、迅速且つ正確に、刊行作業を進めてくださいました、穂高綜合印刷所の沖健吏様、まことにありがとうございました。 信仰の揺藍期、愛を持って見守ってくださった、懐かしい故岩田先生ご夫妻、不安の中にあった私を、寮生として温かく迎え入れてくださった京都御幸町教会の皆様、ばかばかしくも懐かしく、共に喜び共に泣いた寮生の皆様、穂高教会伝道師時代お世話になりました、故高地先生ご夫妻、風変わりな私を忍耐強く受け入れてくださいました、復活之キリスト教団と穂高教会の皆様、また、藤木先生の説教を聴き、愛の主を礼拝するために、遠く穂高の地まで全国各地からお集まりくださいました皆様、ありがとうございました。 高齢となった今も、物心にわたり支え続けてくれる、穂高と京都の父母、兄姉たち、同志社合格を知らせてくれた亡き兄、親戚の皆様、友人の皆様、そして、牧師家庭の重荷を共に担っていてくれる妻、子どもたちにも感謝します。 「あとがき」としては長くなり過ぎました。お許しをいただきたいと思います。 2009九年 2月 復活之キリスト穂高教会牧師 毛見 昇(けみ のぼる) |