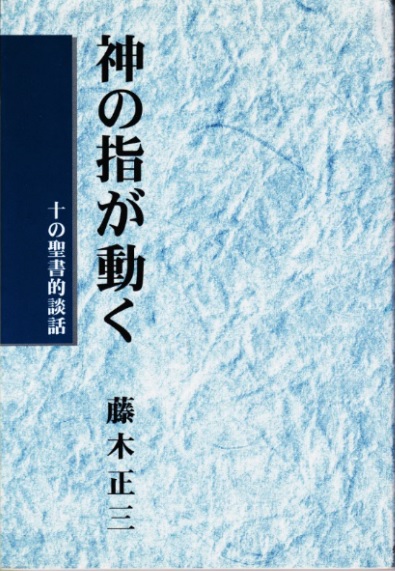|
神の指が動く 十の聖書的談話 Tさん親娘に ――不図 神の指はうごめく―― 天地創造 島崎光正 神は はじめに 天と地とを創造された 地は形なくカオスがその上を覆っていた 地球の柱時計はまだ眠ったままだった 不図 神の指はうごめく (「帰郷 島崎光正遺稿詩集」加藤常昭編教文館) 目 次 マルコによる福音書 5章25~34節 ヨハネによる福音書 2章13~17節 創世記 4章1~7節 ローマの信徒への手紙 12章9~21節 マタイによる福音書 5章43~48節 ルカによる福音書 2章8~20節 マタイによる福音書 23章1~12節 マタイによる福音書 1章18~25節 マタイによる福音書 27章11~26節 ルカによる福音書 24章1~12節 自主決定にあらずして―まえがきに代えて― 自主決定にあらずして たまわった いのちの泉の重さを みんな湛えている この詩は、1997年8月29日ドイツのボンで開催された「二分脊椎国際シンポジウム」で、詩人の島崎光正さん(1919・11・2~2000・11・23)が『私の願い』と題する講演をなさった時、その締めくくりの言葉として紹介されたご自身の詩です。島崎さんがシンポジウムに出席中に、その会場で作られたものだそうです。二分脊椎というのは、生まれながらに脊椎に異状があり、そのため歩行や排尿などに生涯不自由を負わねばならない病気と聞いていますが、次のような言葉で講演は始まっています。 「私はこの度、日本のチームの一人として車椅子に乗りながらドイツにやってまいりました、二分脊椎の障害を負った七十七歳になる男性です。もちろん、私は生まれた時からこの障害を負っていました。そして、両親と早くに離別をしたためにミルクで養ってくれた祖母の話によりますと、三歳の時にようやく歩けるようになったとのことです。七歳となり、すでに足を引きずりながら、村の小学校に入学しました。やがて、市の商業学校へと進みましたものの、間もなく、両足首の変形が急にあらわれましたために通学が困難となり、中途退学をしなくてはなりませんでした。それからは、日本アルプスへの登山客の土産品である白樺に人形を刻むことを職業とするようになりました。同時に、その遅い歩みの中から詩を綴ることを覚え今日に至っております。」 (日本二分脊椎・水頭症研究振興財団機関紙「B&C」Vol.7-6) わたしは島崎さんが日本現代詩人会会員である詩人で、「詩集故園・冬の旅抄」の作者であること、身体障害者であり、日本基督教団の教会に属する信仰者であり、同教団発行の月刊誌「信徒の友」の編集に関わられた方でもあることは知っていましたが、それ以上は知りませんでした。しかし、冒頭の詩を読んだ時、この詩に綴られるまでの島崎さんの苦しい心の旅路の《長さ》がさっと心をよぎって、思わず手を合わせたくなるようなものがありました。 「自主決定にあらずして」、身体的不自由さ、生い立ちの不遇さ、泣こうが喚こうがどうにもならぬわが身に降りかかった不条理、この自主決定にあらざるものを、怒り、嘆き、呪う孤独な迷いの中を通り抜けて、「たまわった」と島崎さんが受け止められるに至るまでの心の旅路の長さ。 さらに、そのたまわったものが、「いのちの泉の重さ」と表現されるほどに、生きとし生けるものを生かす「いのち」そのものであり、そのいのちから湧き出る「泉」のような生かす力であり、そのいのちの力に生かされている生命の尊厳の「重さ」であることに、島崎さんが気付かれるに至るまでの心の旅路の長さ。 そしてもう一つさらに、そのいのちの泉の重さを与えられているのは、自分一人ではなくて「みんな」であり、そのみんなが等しくいのちの尊厳を「湛えている」ものとして見えると共に、自分もみんなの中の一人として見え、相違の彼岸に島崎さんが立つに至られるまでの心の旅路の長さ。 この短い詩を読んだ時に、さっとわたしの心をよぎったのはそういう長さでした。 この詩は、島崎さん七十七歳の最晩年の詩です。島崎さんの一生がかかっている詩です。こういう詩に結実するまで、長く続けられた島崎さんの生きることへの思索、それにわたしは手を合わせたいのです。そしてこの《長い生への思索》こそが、信仰といわれるものの本質ではないか、とわたしは思ったのです。 島崎さんは二十八歳の時、洗礼を受けられたそうです。島崎さんはもちろん生きることへの思索を、その負わされた重荷のゆえに小さいときからしておられたことでしょう。それが信仰によって、そういう人がときに陥りやすい歪みから守られて、健全に深められていき、この詩に綴られているように、人は生きているのではなくて生かされているものであるという事実に心底から開眼するまでに、つまり、人間存在そのものに届くまでに、深められていったのでしょう。そしてわたしは思うのですが、こういう詩の境地にまでくれば、もはやキリスト教とか仏教とかそういう宗教の違いなどは、もう言う必要はないということです。 人間がしているさまざまな営みの中で、宗教が固有のものとしているのは、生きるとはどういうことなのかという生への思索であったと思います。思索とは、経験によらない純粋な思惟である思弁とは違って、行動の指針となるように物事を考える努力のことですから、それは生活を反映し、そして、生活に反映して、生き方をつくり変えるように迫る力を持ちます。そういうものとして思索は、思弁が客観的・教え的な思考であるのに対して、主体的・生き方的な思考です。したがって、主体的・生き方的であるのが本来な宗教は、生きることを存在の深みにまで掘り下げようとする生への思索とは、別ではあり得ないのです。宗教は、生かされているという存在の事実に気付き、生かされているというセンスで生きることを促していく、生への思索なのです。それを生涯のこととして長く続けること、それが宗教の心でした。 ですかち、もしこの生への思索が宗教からなくなれば、宗教は思弁的となり、教えとなり、教えとして語られ、教えとして理解され、教えとして受け入れられ、そして、そのことがそのまま信仰を持つことそのものを意味すると、誤解されるようになるでしょう。さらに、神や救いについての教え(教会の思弁的イデオロギー)となったその宗教は、律法的になり、党派的になり、そして、必ず人間を疎外し、人間を抑圧するものになるでしょう。 生きとし生けるものはみんな、どのような生きる軌道を与えられようとも、一つの大いなるいのちに生かされた生命であり、その根源の一つのいのちより湧き出たものとして、みんな尊く重い生命なのです。島崎さんの詩には、この生命への思索があります。思弁ではなくて思索があります。そして、その思索の果てにたどり着いた思想があります。《生かされて生きる=被の思想)があります。そして、この被の思想は諸宗教が目標としている境涯であり、従って島崎さんの思想は、諸宗教に通底する宗教の思想と言ってもよいものなのです。 人間は、生かされたものとして心ならずも負わされたものを負いながら、それを受け止めて生きるより仕方のないものです。そのことが飲み込めなくて、いろいろ注文をつけ、期待外れに苛立ち、そのため、かえってわたしたちは悩みを呼び込んで生きています。そして、救いを求めています。 島崎さんの言葉を使えば、「自主決定にあらざるもの」を負うて生きているのが、「いのちの泉の重さを湛えている」「みんな」の姿であり、それを受け止めて生きるのが人間の本来であるのに、わたしたちはそれが分からなくて、それを避けて生きようとしてかえって苦悩を呼び込み、救いを求めているのです。 ですから救いは、「自主決定にあらざるもの」を避けるところにはなくて、それを「たまわったもの」として受け止め、そこを生き場所として、そこで咲こうとすることにあるのです。それは諦めた弱い生き方ではなくて、生かされていることへの誠実なのです。生かされているものとして覚めている、地に足の着いた生き方なのです。そしてそれが宗教の、そして宗教のみが示し得る答えです。 島崎さんの信仰は、「自主決定にあらざるもの」を負った長い苦しい生への思索の旅そのものでした。そして、それは宗教の思想である被の思想にたどり着いています。それはわたしたちが生活を委ねるに足るものの見方であり、まさに《生の思想》です。だからこそ、キリスト教の信仰に拠りながらキリスト教の枠を超え、さらには宗教の枠を超えて、すべての人に届く生きた力を島崎さんの詩はもつのです。 聖心会シスター鈴木秀子さんも言っています、「神は、あなたを何処へ導くのでしょうか。神はあなたを、いま、あなたのいる場所へ導いています。いま、あなたのおかれた場で、あなたは、かけがえのない存在として、目に見える世界を突き抜けて、真の現実を見、真の人間性を発揮するように導かれているのです。」(「神は人を何処へ導くのか」三笠書房)。 神は、自主決定したのではない「いま、あなたのいる場所」から救い出すのではなくて、まさに、その場所で「かけがえのない存在」として自分が見えるように導く、そういう大いなるいのちです。ですから宗教は、どの宗教も、生かされたところを受け止めて生きる被の思想として通底するものなのです。 そういうものとして、宗教はそれぞれの優位性を主張するよりは、そうなりがちなのですがそうではなくて、キリスト教は、特にそうなりがちなのですがそうではなくて、生への思索を、長く続く生涯の課題として自らに課して生きているか否かをこそ、自らに問わねばなりません。その自問が信仰に内実を与えます、宗教をその名に相応しくします。 自主決定にあらずして たまわった いのちの泉の重さを みんな湛えている * 引退して十年になります。この間、機会を与えられてお話したものから選んで、1999年に「系図のないもの―聖書的独白録―」(近代文芸社、ダビデ社)としました。本書はそれ以後のものから選んだものです。 わたしの聖書の読み方「独白」については、先の書の「まえがき」に記したとおりですが、同趣旨のことを少し表現を変えて記しておきます。 福音は神の言葉として一つです。しかし、それが本当に生きた言葉として受け取られる時、一人一人の悲しみ、苦しみに触れて、寄り添い支える《わたしにとっての福音》となり、自ずから多様なものにならざるを得ません。それが生かす真理としての福音の姿です。だから人は自分の問題を引っ提げて、他人はいざ知らずわたしはこう聞くと、わたしの心に納得するよう聖書に接することが求められます。いずれにしても聖書を読むにあたって、わたしを前面且つ全面に、押し出すことです。神の言葉が語りかけている相手はほかの誰でもない、このわたしなのですから。 一体、宗教とは人間の存在の究極を追求し、そこでの人生態度、すなわち、《生かされているものとして生きる》を実現しようとするものです。その場合、人間とはほかならぬわたし自身のことでなくてはなりません。わたしの生き方に成就しないような宗教的真理など全く空疎です。ですから、もし信仰を求めようとするならば、まず《わたしに向き合う》ことから、それを始めねばなりません。そして、丁寧に正直にわたしに向き合い続ければ、エゴに囚われているわたしが見える、正確に言えば、わたしのそのままを見せてくださっているいのちに、包まれて生かされていることに気付いて、そういうわたしが見える、そのように人間はできているのです。従って、わたしに向き合う道は、いのちにすっぽり包まれているわたしが見えるほどに、あるいは、そういうわたしが見えるまでに、私的に徹して《ただ内を観続ける》ことなのです。宗教的救いとは本来、《見せられているわたしに素直になること》にほかならないのであり、それは、私的な問題から始めて私的な納得に落ち着く類いのものなのですから、そうなります。私的に徹してただ内を観る、それが宗教の生命と言ってよいのではないでしょうか。 そして、わたしの問題を引っ提げて、聖書を手がかりに、ただ内を観ながら、素直な生き方を求めて自由に思索する、それが信仰の生きた姿であり、《聖書は結局、そういう思索を、自分の都合で勝手に、中途半端に止めることを許さない力を持って迫る宗教的古典》、そうわたしは思っています。 本書は、「説教集」ではありません。聖書を読みながら観て納得した《わたしの内》を、わたしの言葉で語った「聖書的独白録」であり、「聖書的談話集」です。 (聖書は、日本聖書協会・新共同訳によります。) * 最後になりましたが、島崎光正さんの詩を引用することを、快く許してくださった夫人島崎キヌコさんに、御礼申し上げます。本書をまとめるに当たって、島崎光正さんの、深く長く続いた生への思索に感動しているものが、終始わたしの中にありました。 著 者 2003年8月31日 |